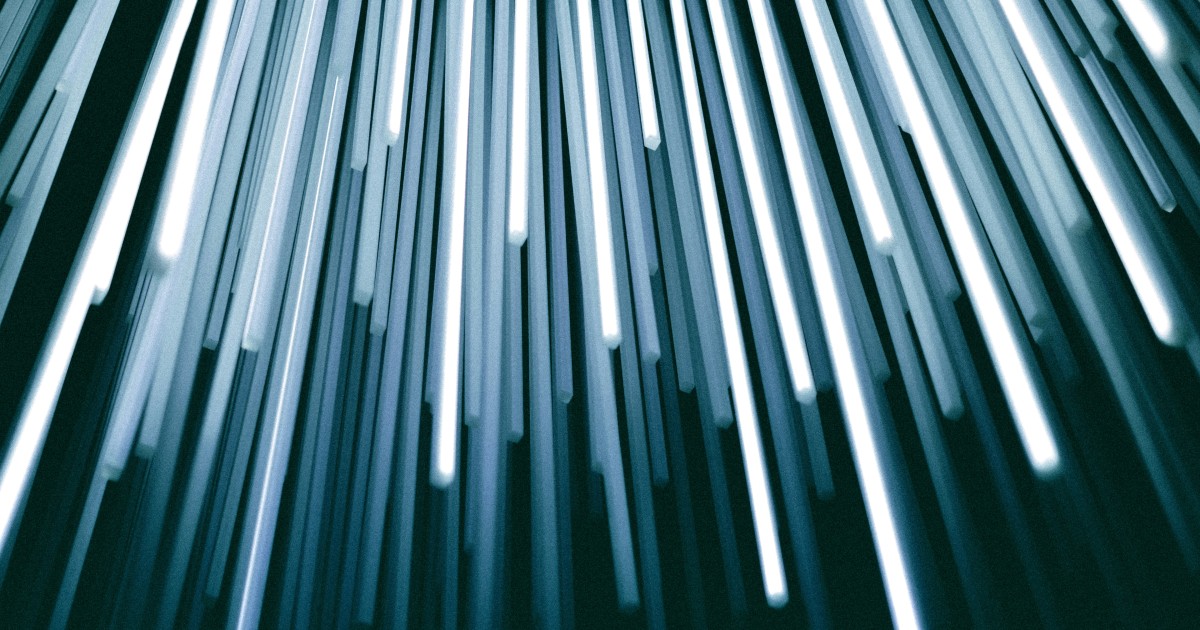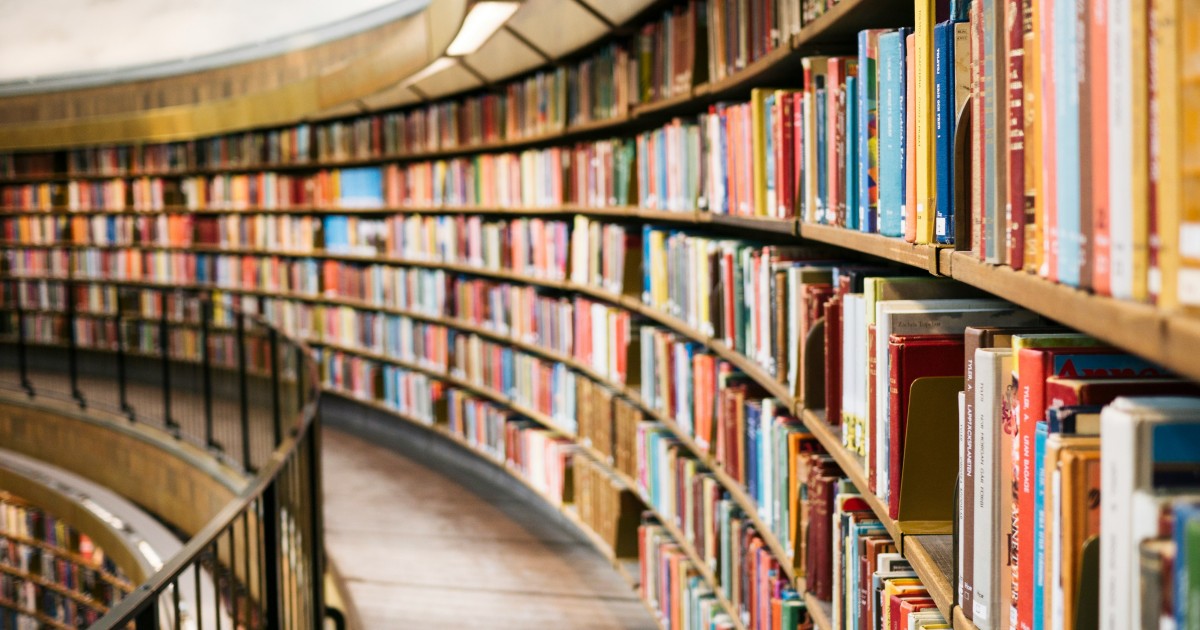ブルーの歴史【第31号】
いつの時代もアーティストを魅了してきた青顔料(ブルー)と化学者たちのお話
いち
2021.07.02
読者限定
【140字まとめ】いつの時代もアーティストを魅了してきた青顔料(ブルー)は,化学者たちの挑戦の結晶でもあります.この号ではフェルメールのブルー,エジプトのブルー,広重のブルー,藍染,呉須,あの国宝の青,そして最先端の「ブルーティフル」まで取り上げます.最後にちょっと珍しい「ブルー」の使い方も.
いちです,おはようございます.
今を遡ること12年前の2009年,およそ80年ぶりに新しい「ブルー」が発見されました.この新しいブルーは「インミン・ブルー」と呼ばれています.本誌【第15号】で少しだけ触れたこの新しいブルーについて,本号では深堀りしていきたいと思います.

この記事は無料で続きを読めます
続きは、10069文字あります。
- 人類が見たブルー
- 古代エジプトのブルーとフェルメールのブルー
- 漢のブルー
- マヤのブルーと日本のブルー
- 広重ブルー
- アズライト(岩紺青)
- コバルト・ブルー
- 曜変天目茶碗
- 合成ウルトラマリンとブルーLED
- インミン・ブルー
- ステーキもブルー?
- おすすめ書籍
- おすすめTEDトーク
- Q&A
- 振り返り
- あとがき
すでに登録された方はこちら