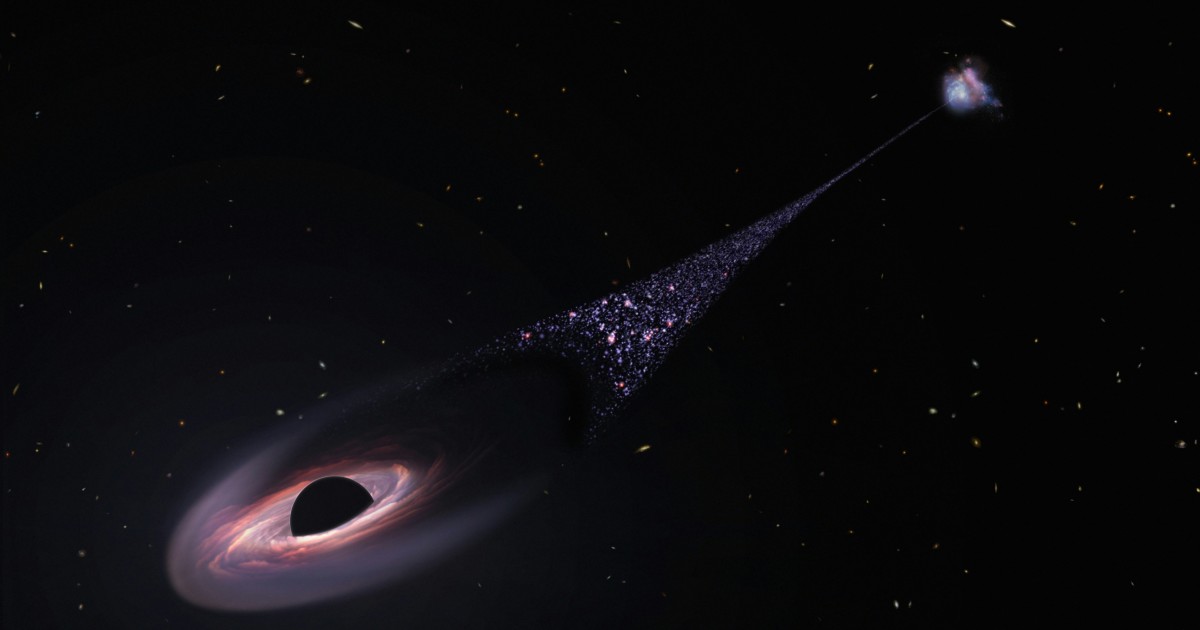【第15号】色を混ぜるとはどういうこと?
加法混色と減法混色の違いとは?
いち
2021.03.26
読者限定
いちです,おはようございます.
このニュースレター『STEAM NEWS』は毎週金曜日朝7:00にお届けしています.
すでにお気づきの方もおられるかと思いますが…実は本日配信予定だった【第14号】を間違って木曜日に配信してしまいました.僕はニュースレターを配信プラットフォームにアップしたら,まずは自分宛てにテスト送信して,修正して,またテスト送信してというのを数回繰り返して本番送信に備えるのですが,今回は間違って1回目のアップロードで配信してしまいました.
誤字脱字はもちろんのことなのですが,流れの悪い部分なんかもテスト配信してから気づくことが多いのですよ.なぜなんでしょうか.
というわけで,いきなりメールが届いてしまった皆様,いつもより誤字が多いとお気づきの方,どうか笑ってお許しください.(ウェブ版では若干修正をしています.)