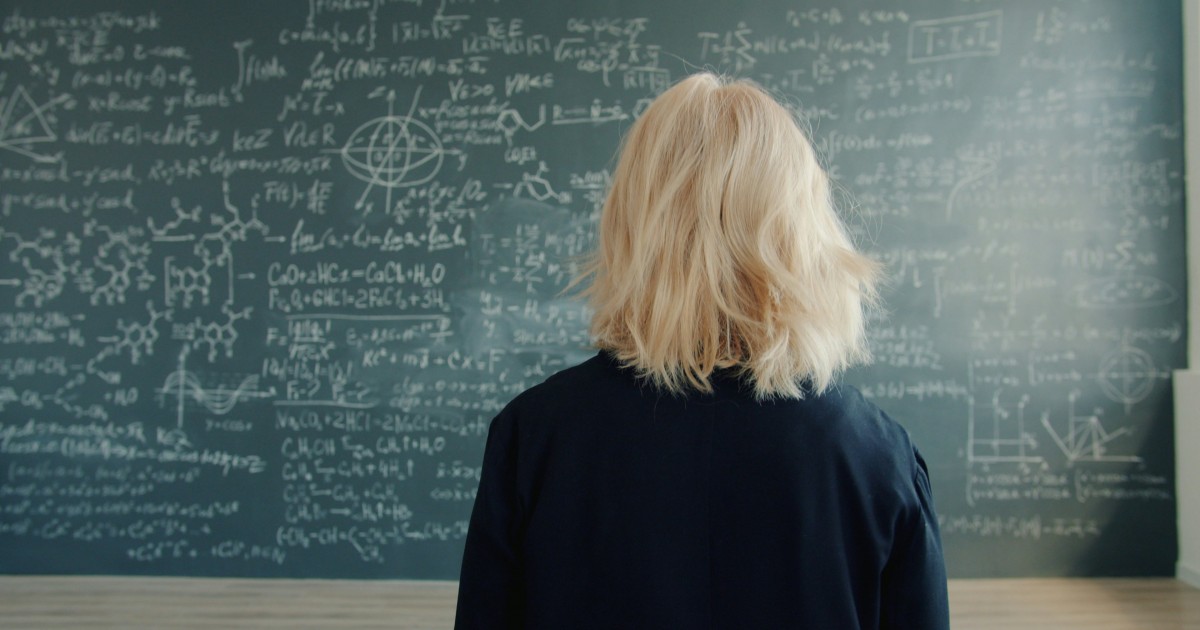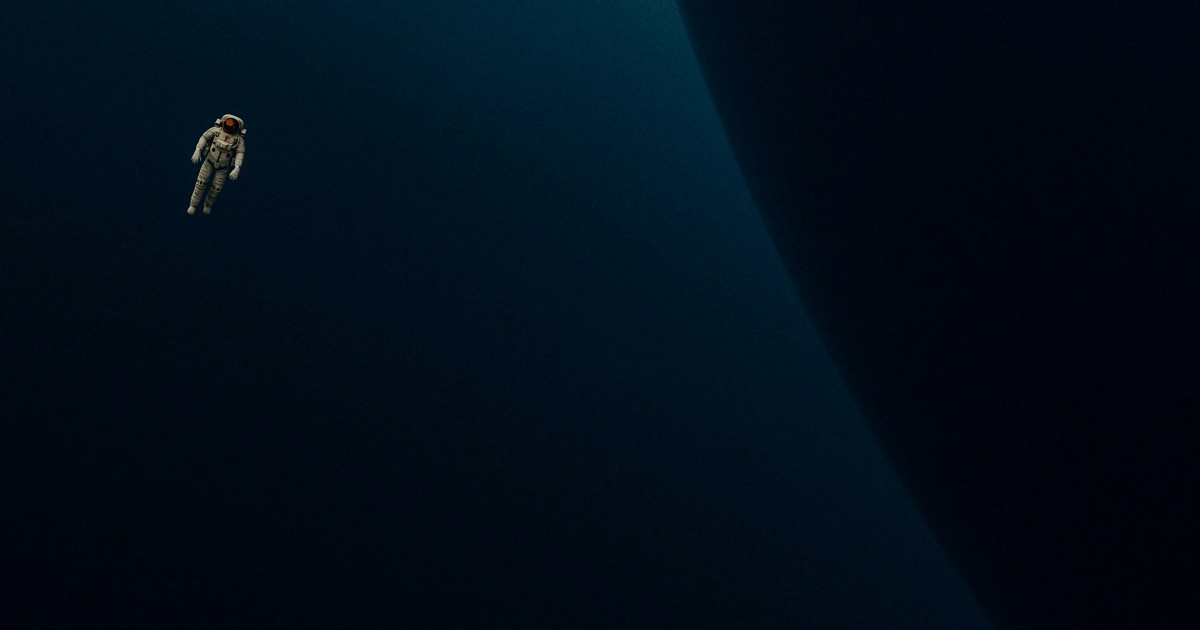【第14号】くたばれ!ゲーテの色彩論〈後編〉
詩人ゲーテが「色彩」について犯した間違い〜いよいよ核心へ
いち
2021.03.25
読者限定
いちです,おはようございます.
今週は「くたばれ!ゲーテの色彩論〈後編〉」をお届けいたします.〈前編〉をまだお読みでない方は,是非こちらから〈前編〉をお読みください.
〈前編〉では触れられなかったのですが,文豪ゲーテが残した「色彩論」は今でも美術教育に強い影響を残しています.ゲーテの「色彩論」が科学的に正しい内容だったなら,なんの問題もないのです.そうではなく,ゲーテの「色彩論」は科学的に見て間違いだらけなのです.
しかし,ゲーテの「色彩論」に触れる前に,簡単にこれまでの内容を振り返っておきたいと思います.

この記事は無料で続きを読めます
続きは、10993文字あります。
- ニュートンの「光学」
- ゲーテの「色彩論」
- ニュートンへの批判
- 色覚はどこから来たのか
- ユニーク・グリーン
- 「黄い」じゃなくて「黄色い」
- 生き残るゲーテの色彩
- おすすめ書籍
- おすすめTEDトーク
- Q&A
- 振り返り
- あとがき
すでに登録された方はこちら