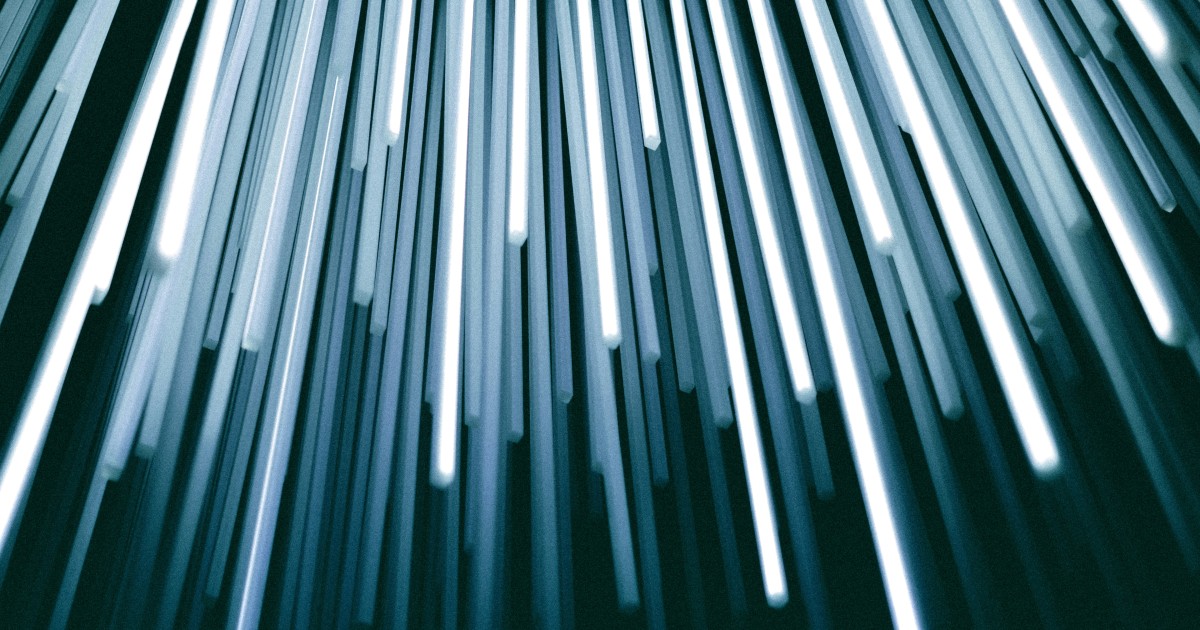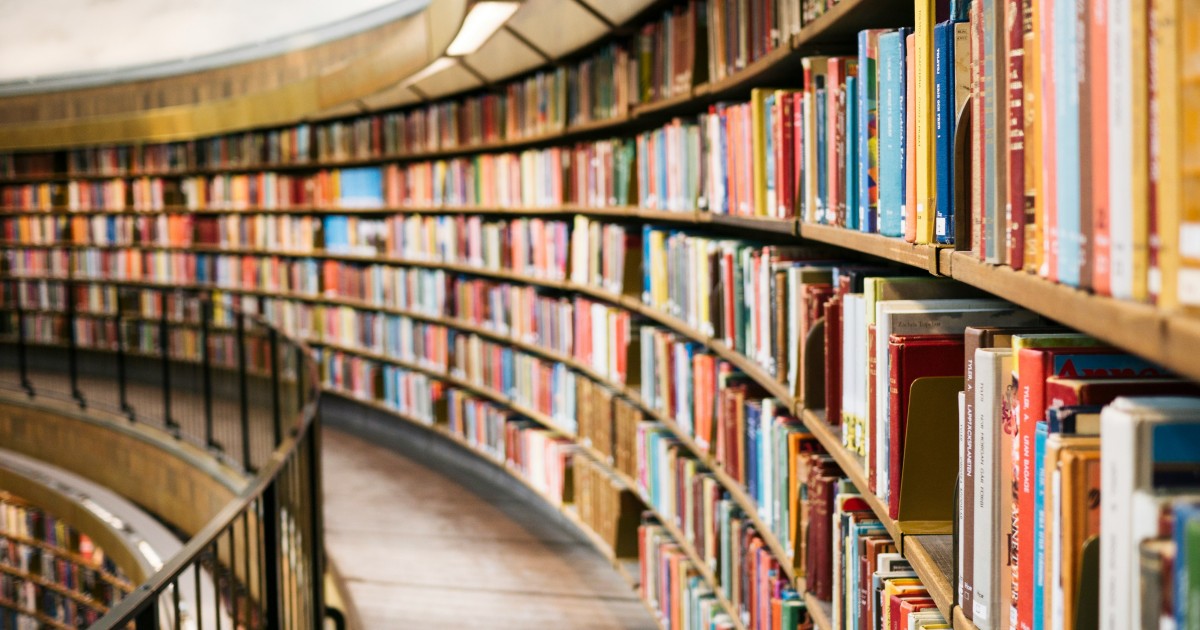天国を観察した科学者ガリレオ・ガリレイ【第133号】
2️⃣ガリレオの観察は神話を地上へと取り戻す営みでした
3️⃣神話と人間をつなぐものは「観察」なのです
いちです,おはようございます.
今週,アップルの開発者向け年次大会WWDCが,カリフォルニアのアップル本社で開かれました.

アップルVision Pro装着イメージ.ユーザの目の部分は外部ディスプレイに描かれたCGです.
このWWDCでアップルは新製品「Vision Pro(ビジョン・プロ)」を初公開しました.Vision Proは頭に装着するコンピューターで,単体でデスクトップコンピューターのように使うことができます.学生の頃,研究室の先輩が数キログラムもある超巨大ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を被り,さらにデスクトップコンピューターをカートに乗せてごろごろと引っ張っていたことを思い出すと,テクノロジーは30年で昇華していくものだなあと感じます.
Vision Proで僕が一番気になった機能は,装着者の目元をCGで再現して外向きディスプレイに表示する「逆パススルー」技術でした.アップルは本技術をEyeSight(アイサイト)と呼んでいます.CGの研究者が言うのもアレですが,フェイクの顔をメガネの上に表示するのって,目元から感情を読み取る文化を持つ日本や他の東アジア各国ではどのぐらい受け入れられるのか関心があります.意外とこういうところから文化は変わっていくのかもしれませんが,暗い部屋だと目だけ光ってるんですよね……?
さて,この号では「観察」をテーマに,本誌【第100号】「科学者をリレーした『時間』のバトン」でご紹介した科学者ガリレオ・ガリレイを改めて取り上げたいと思います.
📬 STEAM NEWS は国内外のSTEAM分野(科学・技術・工学・アート・数学)に関するニュースを面白く解説するニュースレターです.
《目次》
-
ガリレオが見上げた空
-
望遠鏡と月・木星・土星
-
太陽
-
ガリレオが取り戻したもの
-
今週の書籍
-
今週のTEDトーク
-
Q&A
-
一伍一什のはなし
この記事は無料で続きを読めます
- ガリレオが見上げた空
- 望遠鏡と月・木星・土星
- 太陽
- ガリレオが取り戻したもの
- 今週の書籍
- 今週のTEDトーク
- Q&A
- 一伍一什のはなし
すでに登録された方はこちら