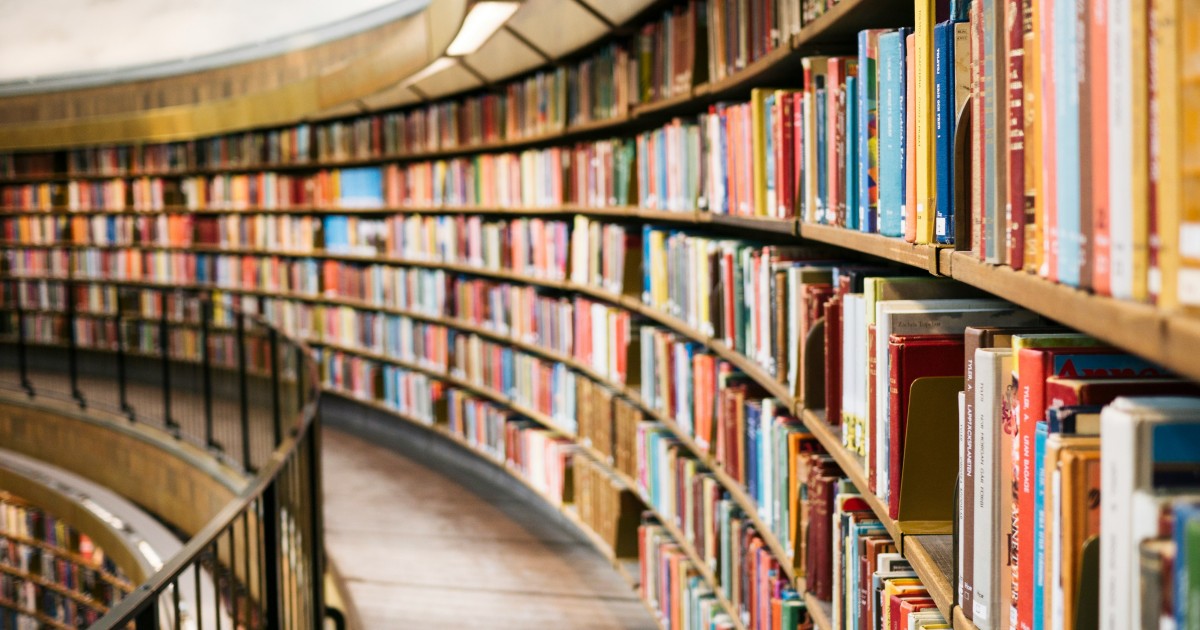【第19号】トリチウムは怖くないけれど…〈読者アンケートあり〉
ニュースでよく耳にする「トリチウム」とはどのような物質なのか
いち
2021.04.23
読者限定
いちです,おはようございます.
2011年の東日本大震災で事故を起こした福島第一原子力発電所周囲の「汚染水」の処理を巡って,先週政府から発表がありました.汚染水から放射性物質を除去した濃度約100万ベクレル/リットルの「処理水」を100倍以上に希釈して海洋放出するというものです.この処理水は,汚染水から様々な放射性物質を取り除いたものとされていますが「トリチウム」は除去しないことが明示されています.
汚染水からトリチウムを除去しなくて良いのでしょうか?
そもそもトリチウムとは何なのでしょうか?
今週は,放射能とトリチウムの話題を取り上げます.

この記事は無料で続きを読めます
続きは、10808文字あります。
- トリチウムとは?
- 放射線
- ベクレル
- シーベルト
- そうは言っても…
- 放射線とアートについて
- おすすめ書籍
- おすすめTEDトーク
- Q&A
- 振り返り
- 読者様限定!アンケートを実施いたします
- あとがき
すでに登録された方はこちら