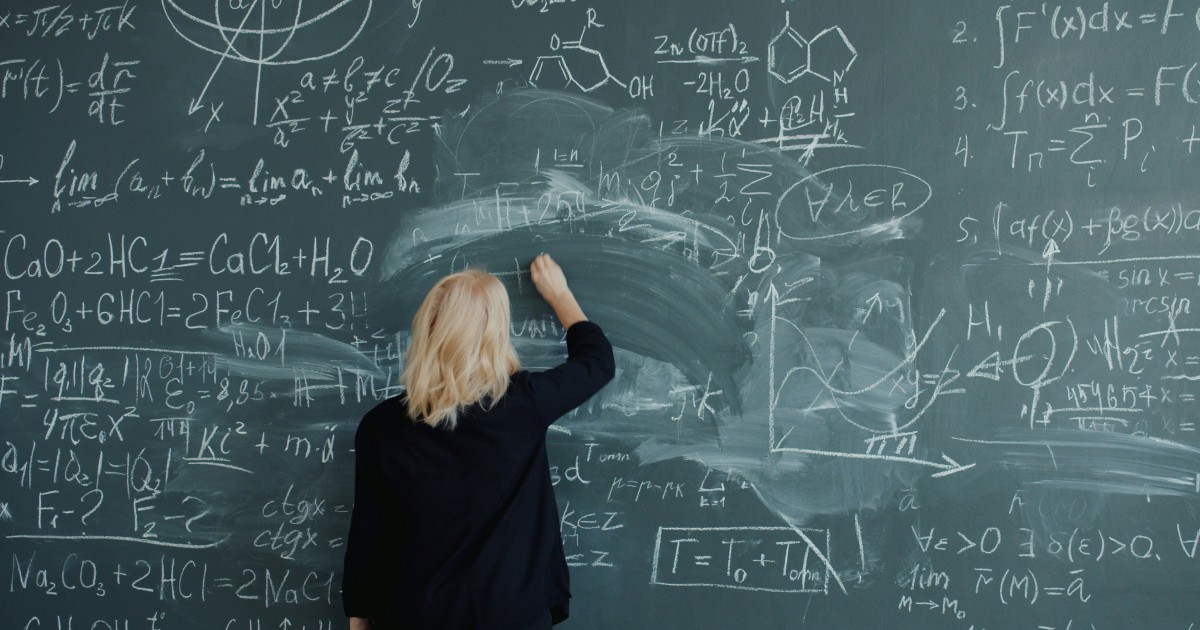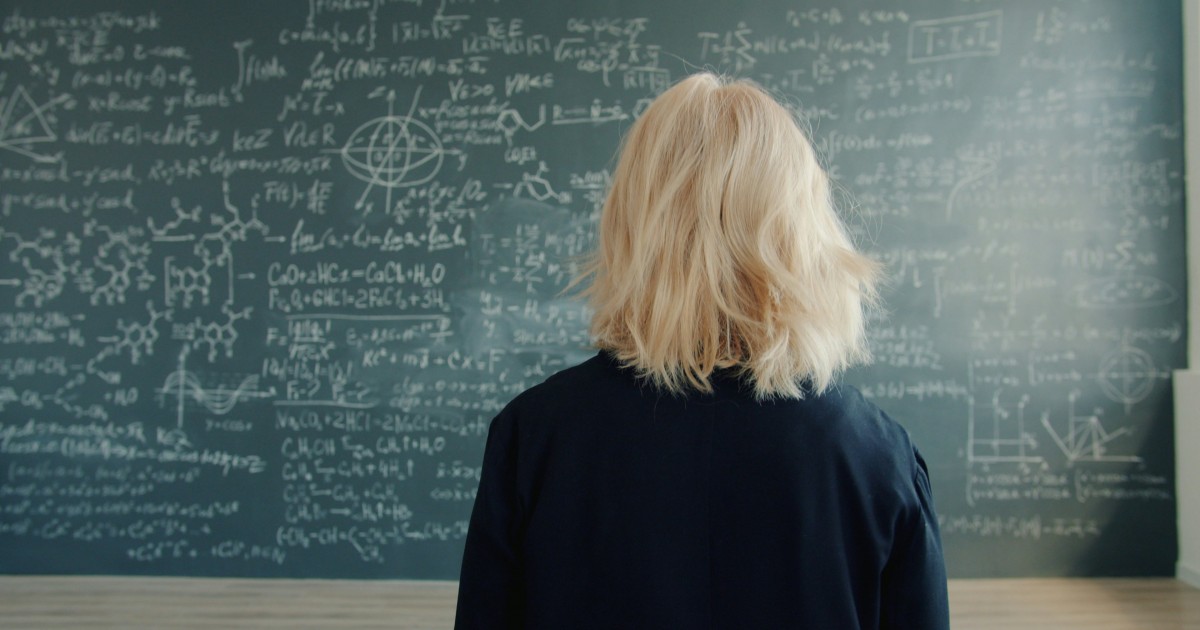【第26号】スパイスと冒険家と化学の物語
【140字まとめ】胡椒・唐辛子・クローブ・ナツメグにまつわる冒険と化学のストーリーをお話します.胡椒が愛された理由,唐辛子が「レッド(赤い)ペッパー(胡椒)」と呼ばれる理由,イギリスがニューヨークを作った理由を書いてみました.あと,化学が見つけたスパイスの共通項もご紹介します.
いちです,おはようございます.
今週は「スパイス」と冒険家と化学に関する小話を3本お届けしようと思います.ひとつ目は「胡椒」.お肉との相性が抜群なスパイスですね.かつては同じ重さの「金」と同価値とまで言われたスパイスです.流石にこれは大げさだったようですが.ふたつ目は「唐辛子」.辛いお料理に必ず入っているスパイスです.こちらはある勘違いから「レッド(赤い)ペッパー(胡椒)」と呼ばれるようになりました.そして最後が「クローブとナツメグ」.ハンバーグに使ったり,単品で生薬として使われたりもします.このスパイスほど,歴史を大きく動かした植物はありません.例えばニューヨークのマンハッタン島は,このスパイスのために島ごと売り払われました.

胡椒,唐辛子,クローブとナツメグの原産地
では早速,胡椒のお話から始めましょう.胡椒と,冒険家バスコ・ダ・ガマと,ピペリンという化学物質のお話です.
スパイス1: 胡椒 — バスコ・ダ・ガマ — ピペリン
胡椒はインド原産のスパイスです.胡椒は紀元前からヨーロッパで大変に珍重されました.ヨーロッパでは胡椒が育ちませんから,当初は陸路をわざわざ運搬していたようです.中世に至るまで,インド産の胡椒は主に現イラクのバグダッドを通り,現イスタンブールを経て,ベネチアまで運ばれていました.
12世紀ごろまでのヨーロッパでは胡椒1ポンド(約500グラム)に奴隷1人分の値段がついていたそうです.なぜそこまで胡椒が重要だったのかについて,多くの教科書が指摘するのが「肉の保存」という理由です.冷蔵庫のない時代,胡椒の持つ抗菌,防腐,防虫作用が肉の保存に決定的に重要だったというわけです.
しかし,僕はこの説を強く疑っています.
断言しますが,肉に胡椒をまぶしても長持ちしません.
ではなぜ当時の人々は胡椒を追い求めたのか.ヨーロッパでは12世紀に入るまでのおよそ1,500年以上,胡椒が超貴重品だったのは何故なのか.「スパイス,爆薬,医薬品〜世界史を変えた17の化学物質」を書いたペニー・ルクーターとジェイ・バーレサンはこう推測しています.
「腐りかけの肉の味を誤魔化すため」
そりゃそうですよね.また当時一般的だった肉の保存方法である塩漬けによってついてしまった強い塩味を和らげる効果も期待されたことでしょう.

この記事は無料で続きを読めます
- スパイス2: 唐辛子 — クリストファー・コロンブス — カプサイシン
- スパイス3: クローブとナツメグ — フェルディナンド・マゼラン — オイゲノールとイソオイゲノール
- おすすめ書籍
- おすすめTEDトーク
- Q&A
- 振り返り
- あとがき
すでに登録された方はこちら