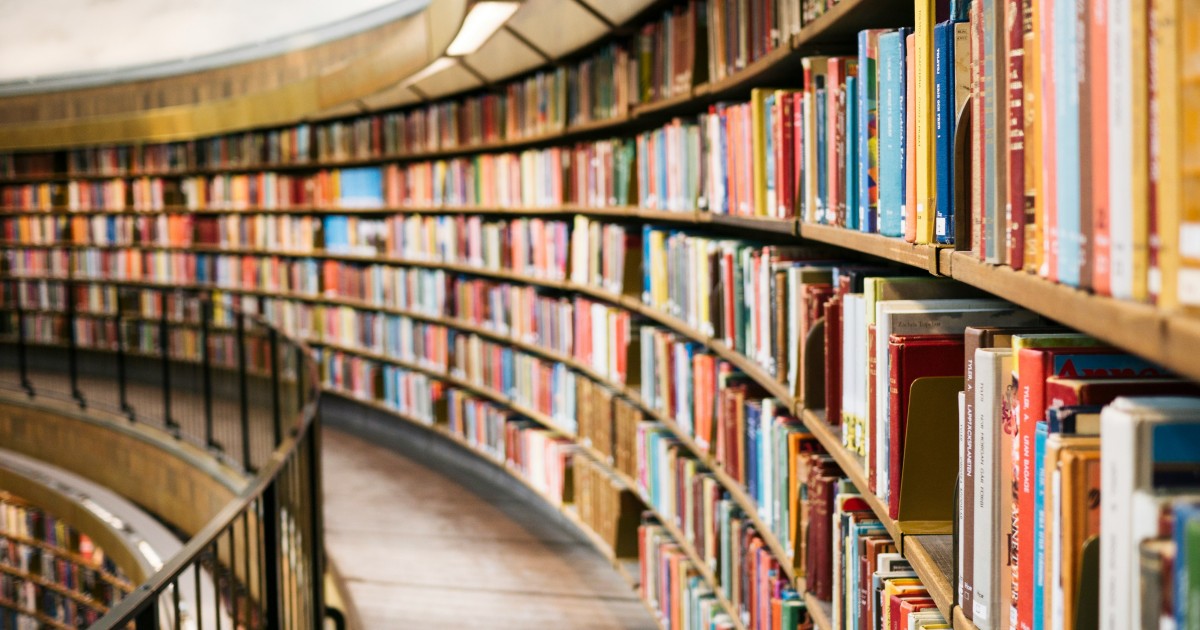超えられる?友達150人の壁【第76号】
【140字まとめ】人類学者ロビン・ダンバーは人間にとって「安定した関係を維持できる上限」が100人から250人の間であるとしました.確かに古代ローマ軍から現代の陸軍に至るまで,最小単位は100人前後です.肉声が届く範囲だからでしょうか.僕は「トイレの問題」のような気もしていますが,さて…
STEAM NEWS は毎週届くニュースレターです.国内外のSTEAM分野(科学・技術・工学・アート・数学)に関するニュースを面白く解説するほか,おすすめ書籍,TEDトークもお届けします.芸術系や人文系の学生さんや教育関係者の方,古代エジプト好きな方に特におすすめです.
いちです,おはようございます.
皆様にお知らせがあります!
このたび TEDxKobe 2022 「回遊」に登壇させて頂くことになりました!詳しくはこちらです.
僕は長年,オーガナイザとしてTEDxイベントに関わってきたのですが,なんと2度目の登壇機会を頂きました.
TEDxKobe や地元の TEDxSaikai のメンバーからフィードバックを貰いながら,毎夜プレゼンテーションを仕込んでいるところです.
仕上がりをどうかどうかお楽しみになさってください.
実は僕も今から「出島」で新しいTEDxイベントを立ち上げるところなんですよね.こちらは TEDxDejimaStudio という名前で,オンライン配信専門になります.こちらでご紹介するアイディアも,ご期待下さい.
【お知らせ】ツイッターで「STEAMコミュニティ」を運営しています.アカウントをお持ちの方は是非ご参加ください.匿名でもご参加いただけます.
《目次》
-
古代ローマの百人隊
-
友達150人の壁
-
ダンバー数から考える国の適切な大きさ
-
おすすめTEDトーク:社会的ネットワークの知られざる影響
-
おすすめ書籍:ドゥームズデイ・ブック
-
Q&A
-
一伍一什のはなし

この記事は無料で続きを読めます
- 古代ローマの百人隊
- 友達150人の壁
- ダンバー数から考える国の適切な大きさ
- おすすめTEDトーク
- おすすめ書籍
- Q&A
- 一伍一什のはなし
すでに登録された方はこちら