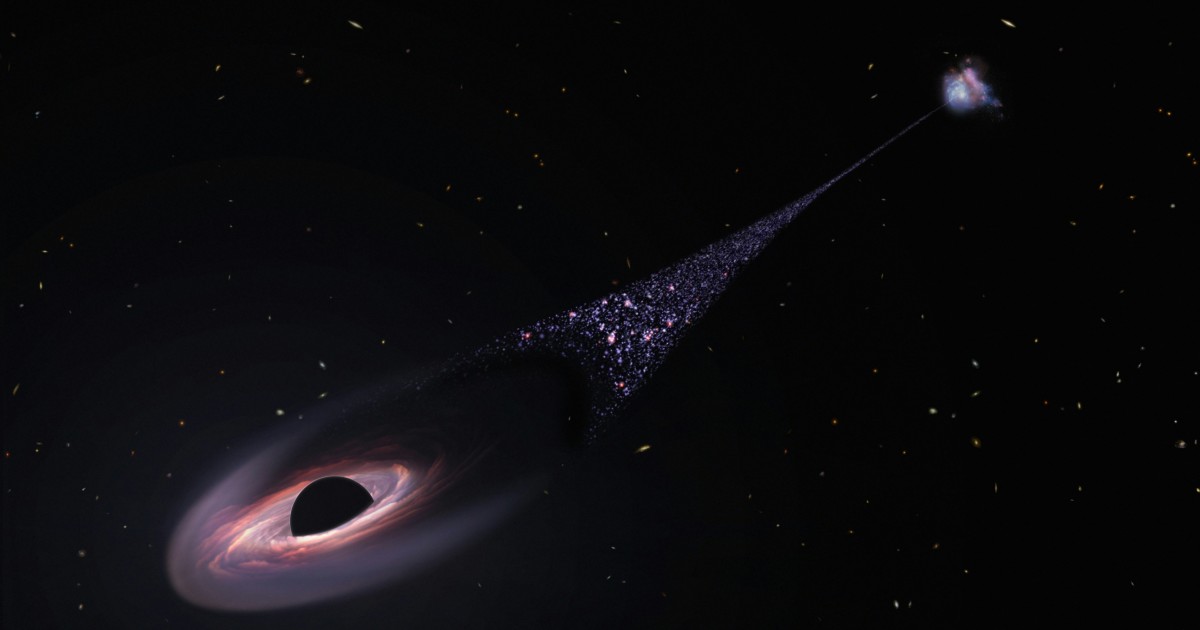漫画村をもう一度考える【第39号】
【140字まとめ】2018年頃に世間を騒がした「漫画村」問題を通して,著作権とインターネットの「ブロッキング」について考えます.ブロッキングはネット上を流れる著作物を「監視」して必要に応じて止めること.ただし憲法で保証された通信の秘密を侵害する行為です.そして現場エンジニアも無視できないのです.
いちです,おはようございます.
9月になりましたね.今月からは「STEAMボート」乗組員(STEAM NEWS有料購読者様)と一緒にレターをお届けして参ります.改めまして,乗組員になっていただいた皆様に感謝申し上げます.
さて,今週はアートに必ずついてまわる「著作権」のお話をしてみようと思います.著作権には様々な切り口があるのですが,この号では数年前に大問題になった「漫画村」の問題を扱います.
今週,コラムニストの小寺信良さんが「結局『漫画村』は死んでないのではないか」という疑問を投げかけられました.
「漫画村」というのは漫画を無料で読めるウェブサイトで,2016年に開設され,2018年に閉鎖されました.漫画村が提供していたのは漫画の違法コピーつまりは「海賊版」で,開設当初から違法性が指摘されていました.
小寺さんの記事から冒頭を引用させていただきます.
2018年ごろ,世間を大いに騒がし,その後の法改正に大きな影響を与えた「漫画村」事件.まだ3年前の話なので記憶も新しいところだが,21年6月2日,福岡地裁にて元運営者に対する判決が出た.著作権法違反と組織犯罪処罰法違反の罪で,執行猶予なしの懲役3年,罰金1000万円,追徴金約6257万円だという.
抗告がなかったため,刑事罰はこれで確定しました.今後は民事で損害賠償が争われる予定です.漫画村による被害総額は3,000億円と見積もられています.
小寺さんの問題提起は,漫画村の類似サイトがまだ活動していること,そして,依然として「漫画村の類似サイトのほうが正規の漫画配信サイトよりも利便性が高いこと」です.一方で,漫画村が活動中に活発に議論されたインターネットの「ブロッキング」については,ある程度決着したのではないかというスタンスでした.
僕も彼と同意見なのですが,おそらく多くの人が忘れかかっている「ブロッキング」問題について,大事なことなので書いておこうと思うのです.
著作権て何だっけ
著作権(copyright)とは「作品」を創作した者が有する権利(right)で,作品がどう使われるか決めることができる権利のことです.では何が「作品」かと言うと,日本では「作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽など」と法で定められています.裏を返すと,単なるデータや,模倣,それに表現を伴わない「アイディア」は作品(著作物)にあたりません.英語のコピー(copy)には「原稿」という意味もあるので「原稿にまつわる権利」でコピーライト(copyright)なのですね.