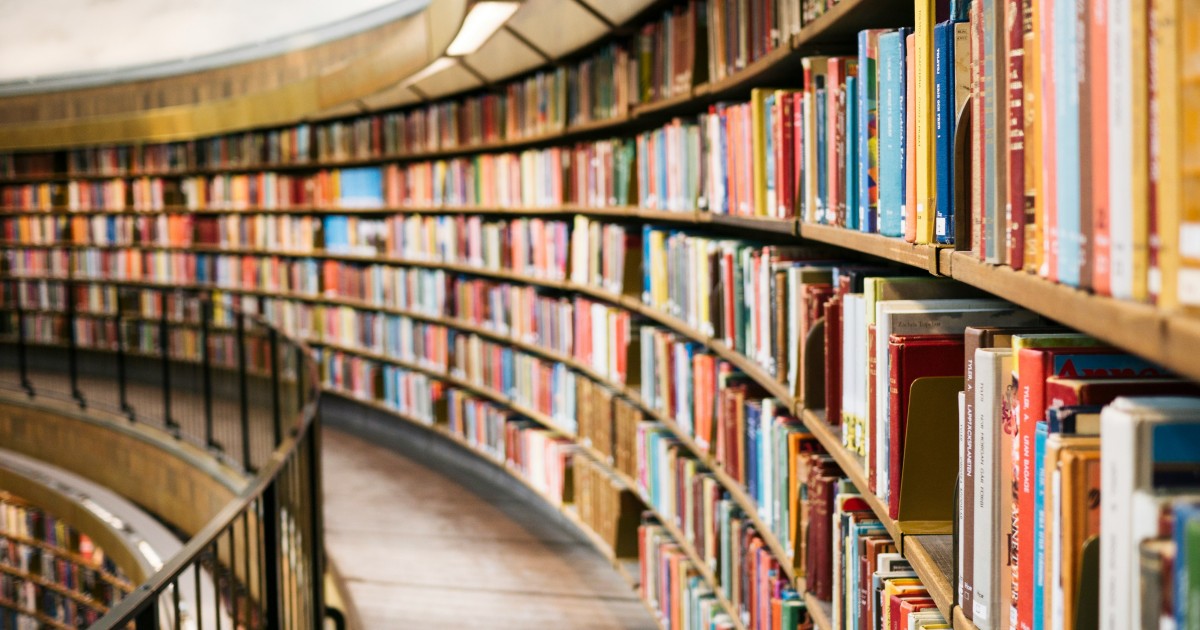【第28号】ビットコインの作者サトシ・ナカモトを追え〈後編〉
ご注意:このレターは「仮想通貨」の購入をおすすめするものではありません.また購入先の紹介や運用ノウハウをお伝えするものでもありません.
ビットコインと同じくブロックチェーンを用いた暗号資産で,相場の急上昇ぶりから「現代の錬金術」とまで言われた「TITAN」は2021年6月17日に「価値が24時間で12億分の1になる」という歴史的な暴落をしています.ブロックチェーンは資産の経済的安全性を担保するものではありません.
【140字まとめ】ビットコインは「ブロックチェーン」という画期的な技術によって支えられています.ブロックチェーンは「ビザンチン将軍問題」を解く,現実的には唯一の手段です.そしてビザンチン将軍問題を解いたことこそが,ビットコインが政府や中央銀行に頼らない通貨である理由なのです.
いちです,おはようございます.
今週はビットコインの仕組みについて,いよいよ核心に触れます.また後半で謎多きサトシ・ナカモトに関する,ちょっとした陰謀説もご紹介させていただきます.
この号は【第27号】ビットコインの作者サトシ・ナカモトを追え〈前編〉の続きです.是非〈前編〉からお読みください.
〈前編〉のまとめ
【第27号】でお伝えした〈前篇〉をまとめてみます.
-
ビットコインは実態がなく,やり取りを記録した「台帳」だけがある.
-
台帳は特定の人物や企業,政府が集中管理しているわけではなく,ビットコインネットワーク参加者全員が同じコピーを持っている「分散台帳」としてのみ存在する.
-
ビットコインネットワークの分散台帳の改ざんはかなり難しい.
-
ビットコインの作者サトシ・ナカモトの正体や生死は不明のままである.
ビットコインは「ビットコインネットワーク」上で共有されている台帳に記載された,コインのやり取りとしてしか存在しません.この台帳には管理者がおらず,ネットワーク参加者全員によってコピーが共有されています.
ここから新しい内容
ビットコインネットワークの参加者はすべて固有の「秘密鍵」を持っています.秘密鍵はパスワードのようなもので,持ち主以外には知られてはならないものです.逆に言うと,秘密鍵を知っていることだけが参加者のアイデンティティということになります.その人の名前や住所,マイナンバーなどは関係ないのです.これがビットコインが高い「匿名性」を持つ所以です.この高い匿名性のために,前号でご紹介した「ランサムウェア」の支払い手段に指定されることも少なく有りません.
ビットコインネットワークの台帳には「XさんがYさんへZビットコイン(BTC)を支払います」という取引記録が書かれます.取引記録は膨大になるので「ブロック」という単位でまとめられます.紙の台帳で言えばページのようなものですね.この台帳には,2009年1月3日の最初の取引を記録したページ,通称「ジェネシスブロック」からすべてが残されています.台帳へのページの追加は個人でもトライすることが出来ますが,ビットコインネットワーク全体で承認されなければなりません.
ここで問題になるのが,過去の台帳の改ざんが無いことを示すことと,取引が正当であることの証明方法です.
Xさんからビットコインを受け取ったYさんは,それが本当にXさん本人のものか確認する必要があります.そのために,ビットコインを送るXさんは,それがXさん本人のものであることをYさんに証明する必要があります.
この目的のため,ビットコインでは,取引に「公開鍵暗号」という暗号の一種を用います.公開鍵暗号とは,メッセージの暗号化と復号にそれぞれ別の鍵を用いる暗号化方式のことです.暗号を金庫に例えるなら,扉を閉じるときと開けるときで異なる鍵を使うようなものです.そして,暗号化,あるいは扉を閉じるときの鍵は全世界に公開してしまうのです.扉を開けるには依然もうひとつの鍵が必要ですから,金庫の安全性は保たれています.この扉を開けるための鍵こそが先述の秘密鍵です.秘密鍵は当然のことながら,他者に公開してはいけません.さもなければ,誰もが金庫を開けられることになってしまいます.

この記事は無料で続きを読めます
- ビザンチン将軍問題
- 現実的な脅威
- サトシ・ナカモトはNSA?
- おすすめ書籍
- おすすめTEDトーク
- Q&A
- 振り返り
- あとがき
すでに登録された方はこちら