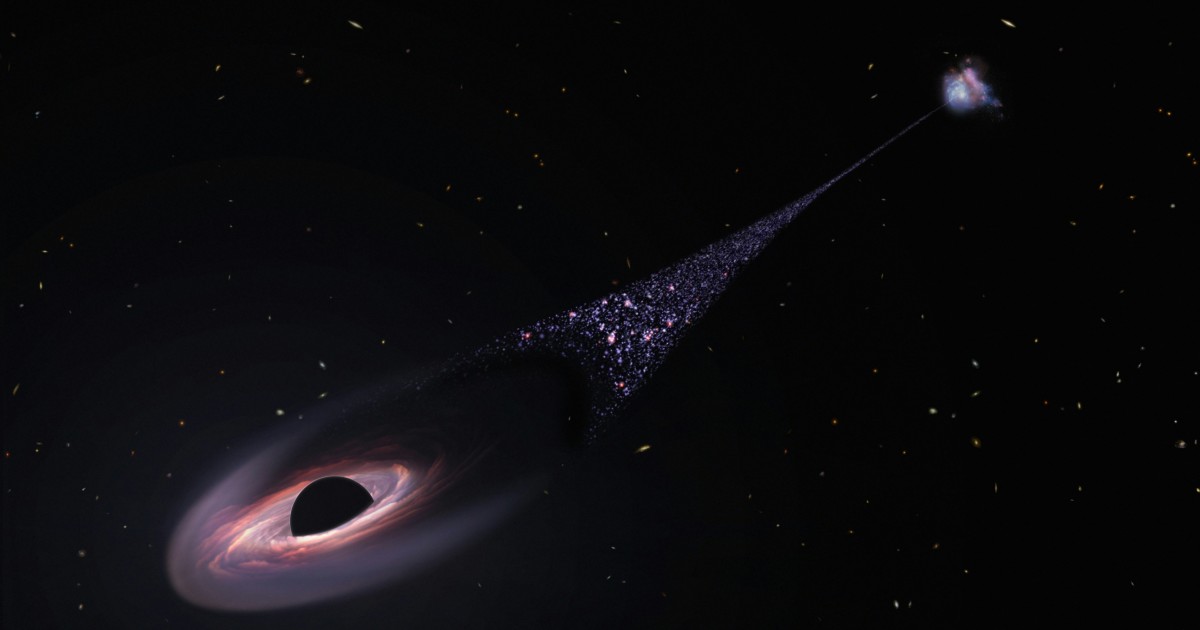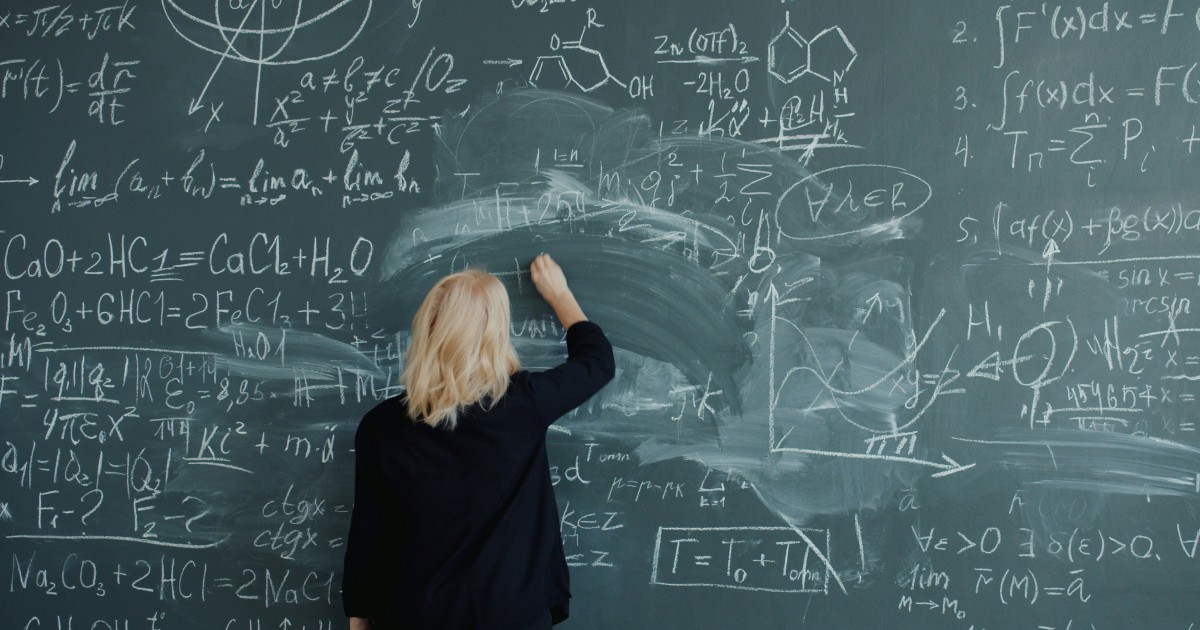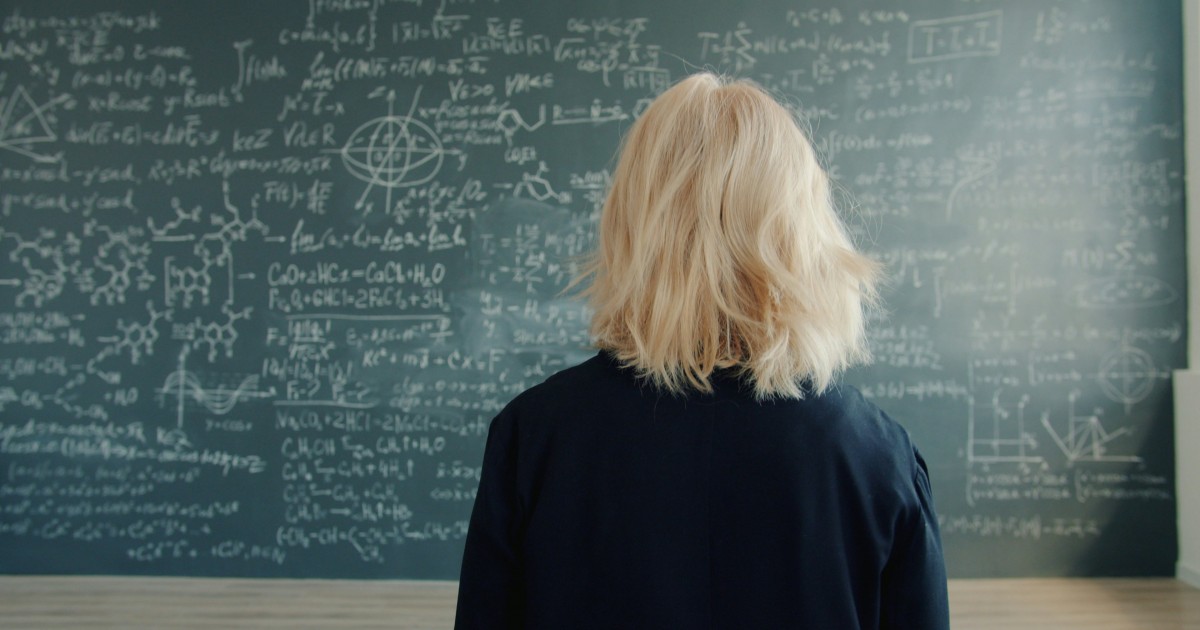ウクライナの数学者「ボロノイ」と琵琶湖の関係【第65号】
【140字まとめ】今週は「ウクライナてどんなところ?」というお話しから,ウクライナ出身の数学者「ボロノイ」の大発明「ボロノイ分割」とその応用までご紹介します.ボロノイ分割は琵琶湖の「救世主」になっているんですよ.最後に,僕たちがSTEMではなくSTEAMを学ぶ理由も書いてみました.
STEAM NEWS は毎週届くニュースレターです.国内外のSTEAM分野(科学・技術・工学・アート・数学)に関するニュースを面白く解説するほか,おすすめ書籍,TEDトークもお届けします.芸術系や人文系の学生さんや教育関係者の方,古代エジプト好きな方に特におすすめです.
いちです,おはようございます.
さて,今週は緊張の度合いが非常に高まっているウクライナを取り上げます.ウクライナは日本からはロシアを挟んで反対側になるため,影の薄い印象がありますが,人口で言えばイタリア,スペインに次ぐヨーロッパの中堅規模の国で,科学技術とりわけ航空宇宙技術はヨーロッパのトップ水準を維持する国です.またウクライナは帝政ロシア,ソビエト連邦時代から数多くの数学者を輩出しています.

ウクライナの恋のトンネル, DmytroChapman, CC BY-SA 4.0
ジョージ・ボロノイはそんな数学者のひとりで,彼の考え出した「ボロノイ図」という図形の作り方は,意外なことに日本の滋賀県の自治体の「救世主」になっています.なおジョージ・ボロノイは Георгій Вороний (Georgy Voronoy) の英語読みで,ウクライナ語だとヘオルギィ・ヴォロニィに聞こえますが,数学の世界で一般的な英語読みで行きたいと思います.
《目次》
-
ウクライナってどんなところ?
-
ジョージ・ボロノイの大発明「ボロノイ図」
-
地球に線を引く人たち
-
ウクライナで起こったこと・これから起こるかもしれないこと
-
おすすめ書籍:旅行写真集ウクライナ
-
おすすめTEDトーク:チェルノブイリに住む理由,それは故郷だから
-
Q&A
-
一伍一什のはなし

この記事は無料で続きを読めます
- ウクライナってどんなところ?
- ジョージ・ボロノイの大発明「ボロノイ図」
- 地球に線を引く人たち
- ウクライナで起こったこと・これから起こるかもしれないこと
- おすすめ書籍
- おすすめTEDトーク
- Q&A
すでに登録された方はこちら