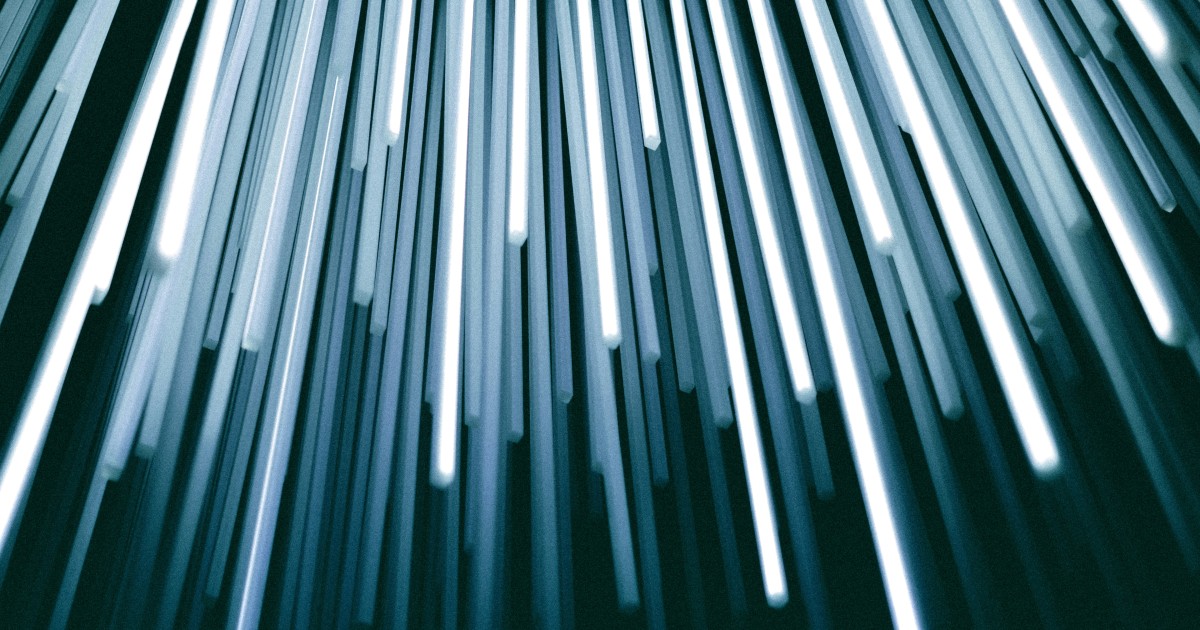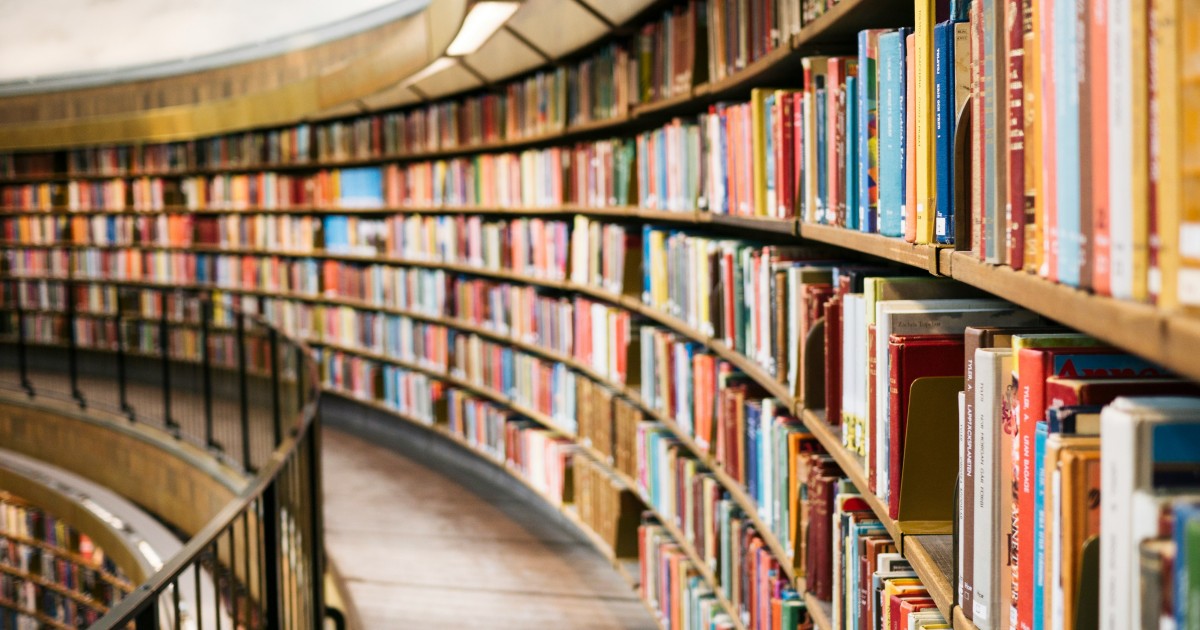太陽からの風と日本の折り紙の意外な関係【第74号】
【140字まとめ】作家アーサー・C・クラークが「太陽からの風」で描いた「ソーラー・セイル」.彼は1963年に「畳み方はまだ知られていない」と書きました.しかしその7年後に日本人の三浦教授が畳み方を発明してしまいます.今週はこのミウラ折りと,キリン「氷結」の缶で使われている構造をご紹介していきます.
STEAM NEWS は毎週届くニュースレターです.国内外のSTEAM分野(科学・技術・工学・アート・数学)に関するニュースを面白く解説するほか,おすすめ書籍,TEDトークもお届けします.芸術系や人文系の学生さんや教育関係者の方,古代エジプト好きな方に特におすすめです.
いちです,おはようございます.
この春から大学生になった皆さんは,授業が一巡した頃でしょうか.
最近は「紙の本」が手に入るうちにと思って古本を買うことが多いのですが,紙の本が無くなる前に,小さな文字を読むという根性が無くなりそうです.電子書籍に慣れてしまうと,紙の本は辛いですね.
さて,今週はそんな古い本から新しい話題をお届けします.
ぜひお楽しみ下さい.
【お知らせ】ツイッターで「STEAMコミュニティ」を開始しました.アカウントをお持ちの方は是非ご参加ください.匿名でもご参加いただけます.
《目次》
-
短編小説「太陽からの風」が描いた未来の宇宙飛行
-
アーサー・C・クラークの想像を超えた「ミウラ折り」
-
宇宙開発から生まれたキリン氷結の缶デザイン
-
もっと勉強したい人へ〜三谷純の折り紙ノートと太陽が失うもの
-
おすすめ書籍:太陽からの風
-
おすすめTEDトーク:宇宙のデザイン
-
Q&A
-
一伍一什のはなし

この記事は無料で続きを読めます
- 短編小説「太陽からの風」が描いた未来の宇宙飛行
- アーサー・C・クラークの想像を超えた「ミウラ折り」
- 宇宙開発から生まれたキリン氷結の缶デザイン
- もっと勉強したい人へ〜三谷純の折り紙ノートと太陽が失うもの
- おすすめ書籍
- おすすめTEDトーク
- Q&A
- 一伍一什のはなし
すでに登録された方はこちら