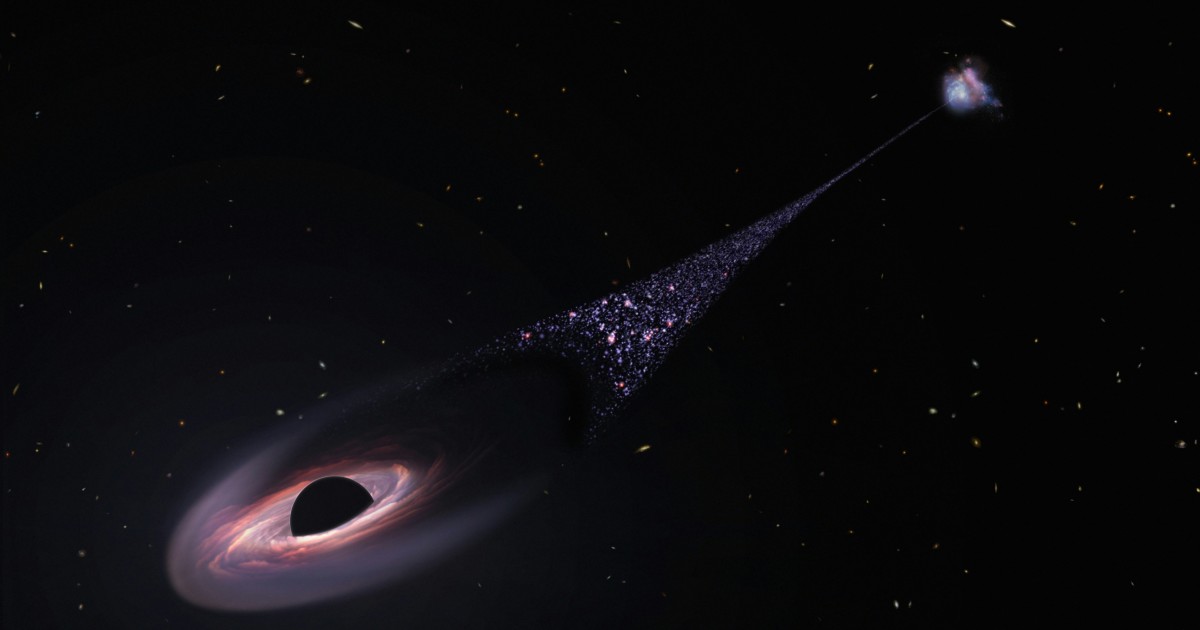【第18号】フランス革命とメートル法
いちです,おはようございます.
普段何気なく使っている「メートル」という単位.日本では計量法によって,長さを表示するときは必ず「メートル」を使わないといけないと決まっています.日本古来の「里」とか「尺」とかを使ってはいけないということですね.
日本政府は1886年(明治19年)4月16日に「メートル条約(明治19年4月20日勅令)」を公布しました.135年前の今日です.この時代はまだ日本古来の単位を使ってもお咎めなしだったのですが,1966年(昭和41年)には厳格なメートル法への移行が政府によって指示されました.当時は随分と行き過ぎた取り締まりもあったようですが,永六輔さんによる「尺貫法復権運動」もあってか,取り締まりは徐々に下火になったようです.
日本で法的に認められている単位は長さのメートルの他に,質量(重さ)の「グラム」,時間の「秒」などがあります.これらの単位は「国際単位系」として世界標準に定められています.もっとも,世界最大の国,アメリカ合衆国だけは国際単位系を使っていません.ほんと,いい加減にしてほしいものです.実際,アメリカが国際単位系を採用していなかったばかりに,1999年に火星探査機を失っています.
この国際単位系,英語では International System of units と言うのですが,略称はISではなくSIです.フランス語の Système International d'unités から来ているんですね.なぜ英語ではなくフランス語由来かと言えば,SIの元になった「メートル法」がフランス発祥だからなのです.そもそも「メートル」だってフランス語なんです.このメートル法は,フランス革命中の1791年にフランス議会で決議されたのです.
メートル法を初めて提案したのはフランスの政治家タレーラン=ペリゴールとされていますが,数学者ニコラ・ド・コンドルセ侯爵とする説もあります.コンドルセ侯爵は「人々が真に平等であるため,また真に自由であるため」に,新しい普遍的な単位が必要だと考えたのです.
この頃,フランスで何があったのでしょうか.

この記事は無料で続きを読めます
- フランス革命
- メートルと古代エジプト
- 質量(重さ)
- 時間と角度
- 日本はどうだったの?
- おすすめ書籍
- おすすめTEDトーク
- Q&A
- 振り返り
- あとがき
すでに登録された方はこちら