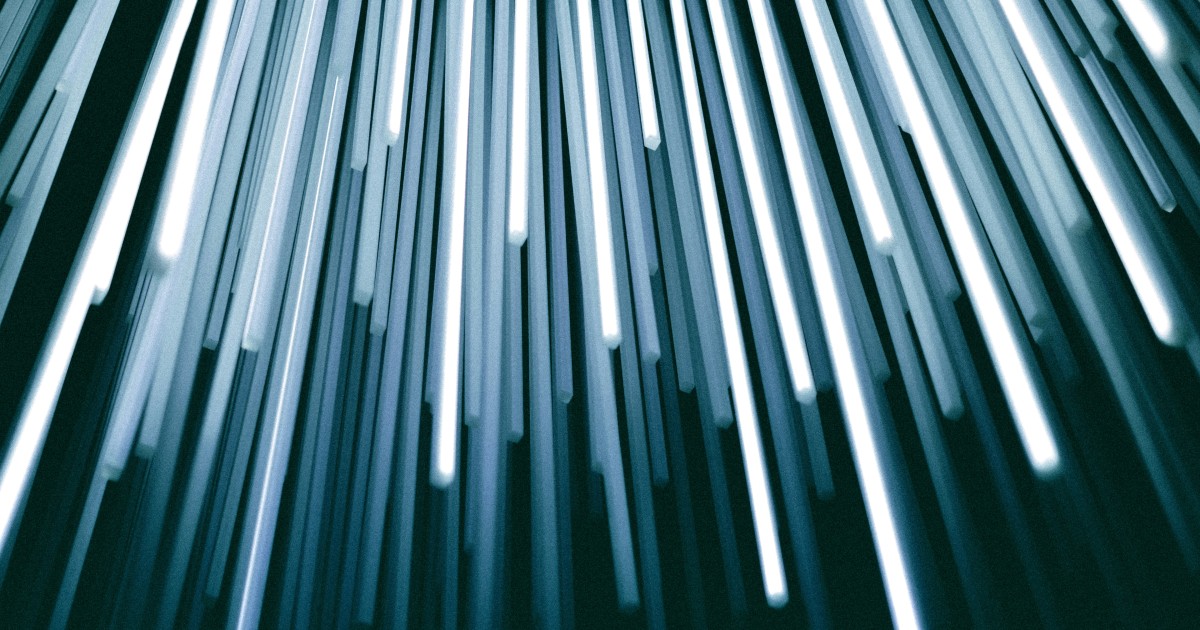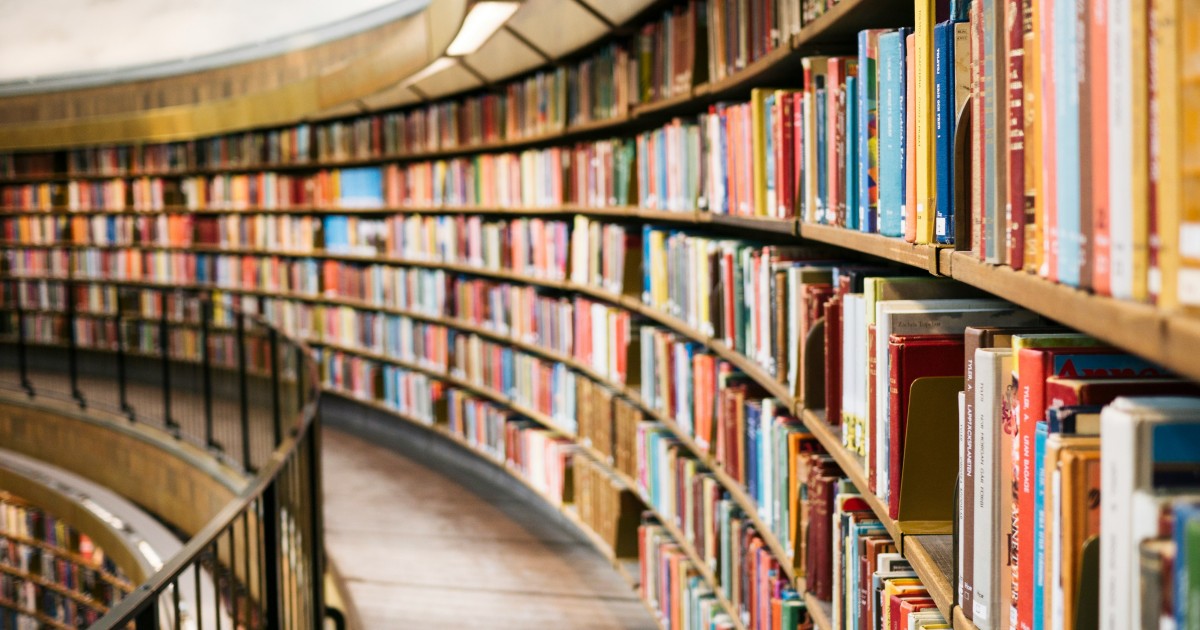【第10号】火星の人
NASAの火星探査機「パーサヴィアランス」が着陸した火星はどんな天体?
いち
2021.02.26
読者限定
いちです,おはようございます.

火星探査機「パーサヴィアランス」想像図 NASA/JPL-Caltech
先週(2021年2月18日),アメリカ航空宇宙局(NASA)の火星探査機「パーサヴィアランス」が火星に着陸しました.2020年7月30日に打ち上げられた探査機で,人類には2年ぶりの訪問になります.火星探査機の歴史は1960年代にさかのぼり,これまでに50機近くが投入されていて,そのうち3分の1ほどが大きな成功を収めています.

この記事は無料で続きを読めます
続きは、11387文字あります。
- 惑星ひとめぐり
- ティコの観測
- 火星人?
- 火星の生命
- パーサヴィアランスが目指すもの
- 有人火星探査へ
- ローウェルにインスパイアされた作品たち
- おすすめTEDトーク
- おすすめ映画
- Q&A
- 振り返り
- あとがき
すでに登録された方はこちら