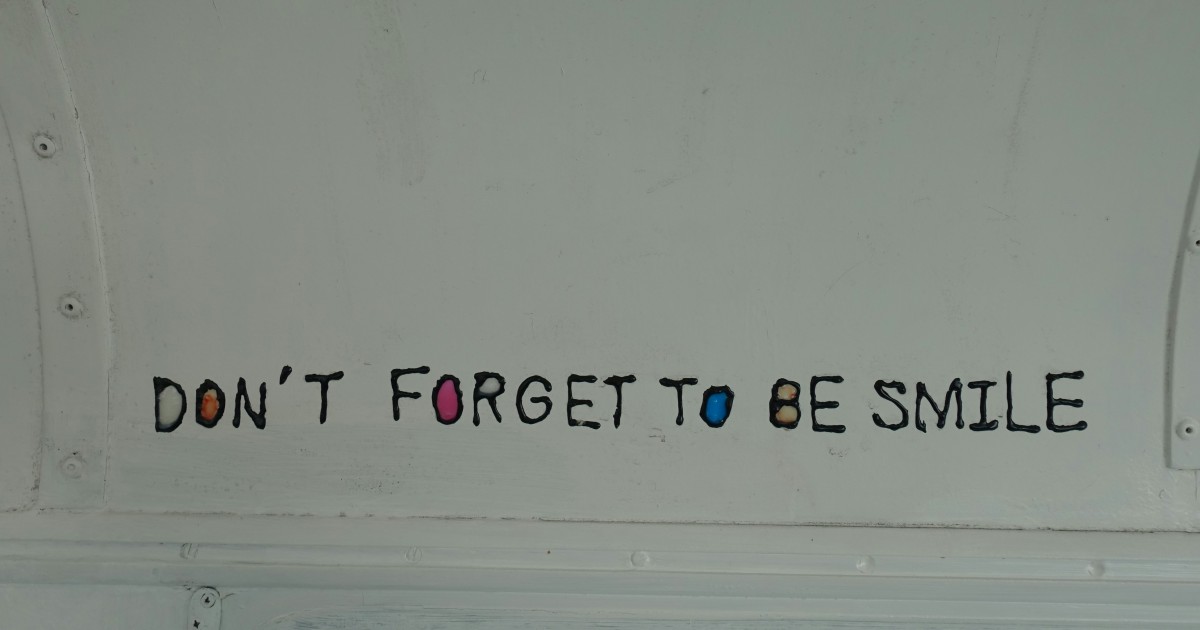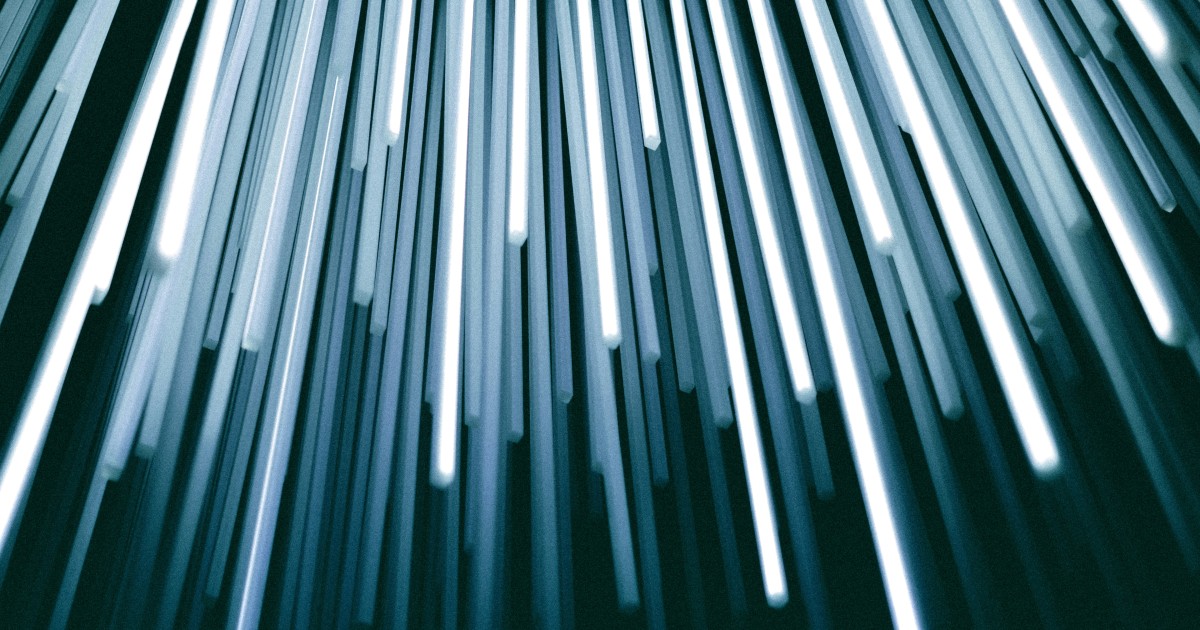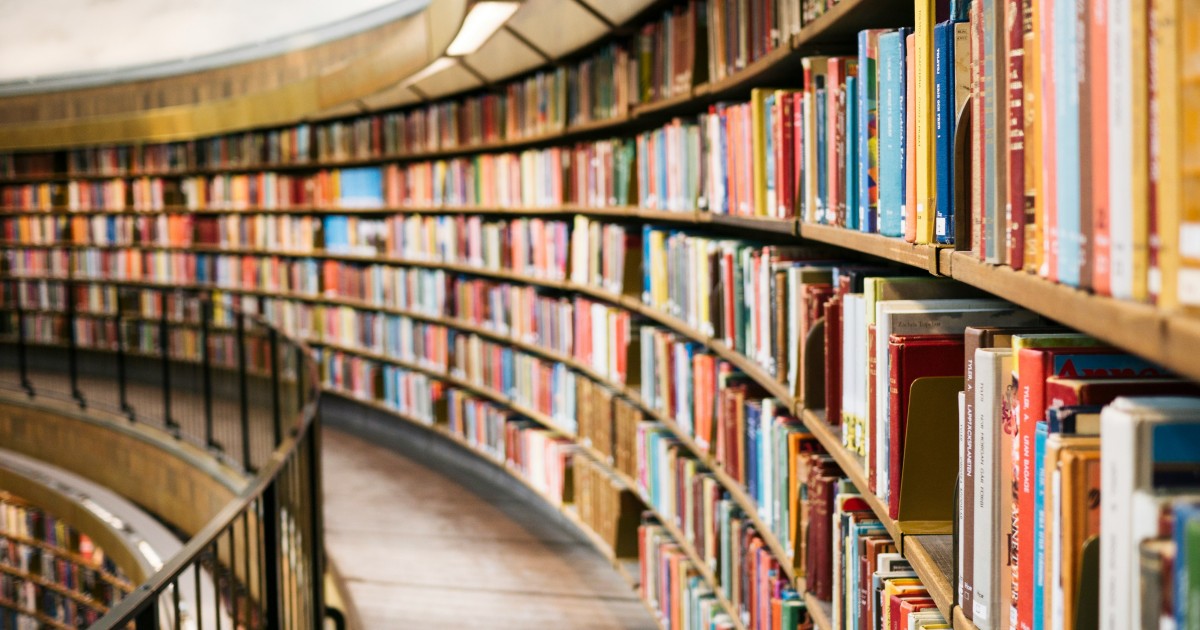腐らせない技術【第155号】
2️⃣人類は食料を腐らせない技術をいくつも開発してきました
3️⃣古代エジプト人は人間を腐らせない方法を発明しました
いちです,おはようございます.
急に寒くなりましたね.僕は急な天候変化に対応できず,1日半ほど寝込んでしまいました.皆様もどうぞお気をつけください.
さて,僕のようなSNS中毒患者が寝込みに何をするかというと,もちろんX(旧ツイッター)です.で,現実の食中毒事件がXを中心としたSNSで騒がれているのを今週は見ていました.

そう言えばですね,僕も中学生のときに部活動の合宿で,見送りに来てくれた先輩からシュークリームを貰ったことがあったんですよね.大変美味しかったです.合宿から戻って「ブルーベリーのクリームがとても美味しかったです」とお礼を伝えたところ「あたし,ブルーベリー入れてないよ」と言われたことがありました.青春の味覚だったのかもしれません.
というわけで,今週はエジプト考古学にも関係する「防腐」技術について,短くお話したいと思います.
📬 STEAM NEWS は国内外のSTEAM分野(科学・技術・工学・アート・数学)に関するニュースを面白く解説するニュースレターです.
《目次》
-
「腐る」てなんだっけ?
-
食料を腐らせない技術
-
ミイラを腐らせない技術
-
今週の書籍
-
今週のTEDトーク
-
Q&A
-
一伍一什のはなし
(Cover Photo by Barbara Chowaniec on Unsplash)
この記事は無料で続きを読めます
- 「腐る」てなんだっけ?
- 食料を腐らせない技術
- ミイラを腐らせない技術
- 今週の書籍
- 今週のTEDトーク
- Q&A
- 一伍一什のはなし
すでに登録された方はこちら