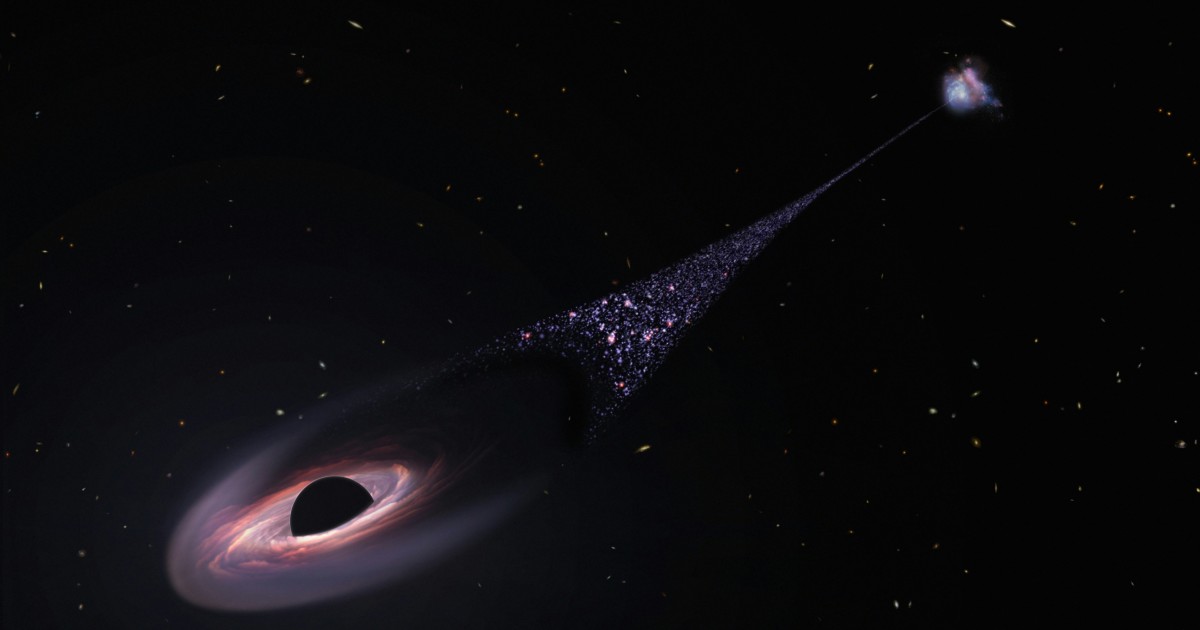議論・討論・談論を使い分けていますか?【第98号】
【140字まとめ】パネルディスカッションに参加してモヤモヤしたことはありませんか?立教大学の中原淳先生が「パネルディスカッションのトホホ文法」として5種類の残念パターンを紹介されています.この号では残念パターンの原因と対策,そして気をつけたい議論・討論・談論の違いをご紹介します.
STEAM NEWS はメールで毎週届くニュースレターです.国内外のSTEAM分野(科学・技術・工学・アート・数学)に関するニュースを面白く解説するほか,今週の書籍,TEDトークもお届けします.芸術系や人文系の学生さんや教育関係者の方,古代エジプト好きな方にとくにおススメです.
いちです,おはようございます.
いまロンドンでこの記事を書いています.
前号をアレクサンドリアからお送りした後,いったん長崎に戻りまして数時間滞在し,再びローマ帝国圏内に戻ってきました.出来ればアレクサンドリアからロンドンへまっすぐ移動したかったのですが,急な日程変更や予算の関係でこのような日程になってしまいました.
ロンドンでは「グローバル・イノベーションのための対話 (Dialogue for Global Innovation)」というシンポジウムの開催をお手伝いさせて頂いています.
ロンドンはコロナ禍がひとまずは収まり,とうか収まったことにして,通常の生活に戻っているようです.時間があればロンドンの様子を撮影してYouTubeに公開しますね.
さて,実は今から数時間後に,科学者,政策学者,経営者,投資家たちとのパネルディスカッションに,僕はモデレーターとして登壇することになっています.
STEAM NEWS購読者の皆様の中にもパネルディスカッションのモデレーターをされる機会のあるかた,パネリストとして登壇する機会のあるかた,あるいはパネルディスカッションを聞きに行ったことがあるけれど「もやもや」だけが残ったという方もいらっしゃるかもしれません.
パネルディスカッションてよく開かれる割に,聞くのも,登壇するのも,回すのも難しいんですよね.
微力も微力ながら,僕も「情報の建築」を考え続けているひとりの研究者なので,この号ではパネルディスカッションの「回し方」について,浅学ながらお話ししてみたいと思います.
そして,最後に以前僕がブログに書いた「大学1年生に知ってほしい『議論』『討論』『談論』の違い」を本記事で改めて紹介します.
本ニュースレターは「STEAMボート」乗組員(STEAM NEWS有料購読者様)のご支援でお届けしております.乗組員の皆様に感謝申し上げます.
【お知らせ】ツイッターで「STEAMコミュニティ」を運営しています.ときどき裏話をつぶやいています.ツイッターアカウントをお持ちの方は是非ご参加ください.
《目次》
-
中原淳先生提案「パネルディスカッションのトホホ文法」
-
議論・討論・談論の違い
-
今週の書籍
-
今週のTEDxトーク
-
Q&A
-
一伍一什のはなし

この記事は無料で続きを読めます
- 中原淳先生提案「パネルディスカッションのトホホ文法」
- 議論・討論・談論の違い
- 今週の書籍
- 今週のTEDxトーク
- Q&A
- 一伍一什のはなし
すでに登録された方はこちら