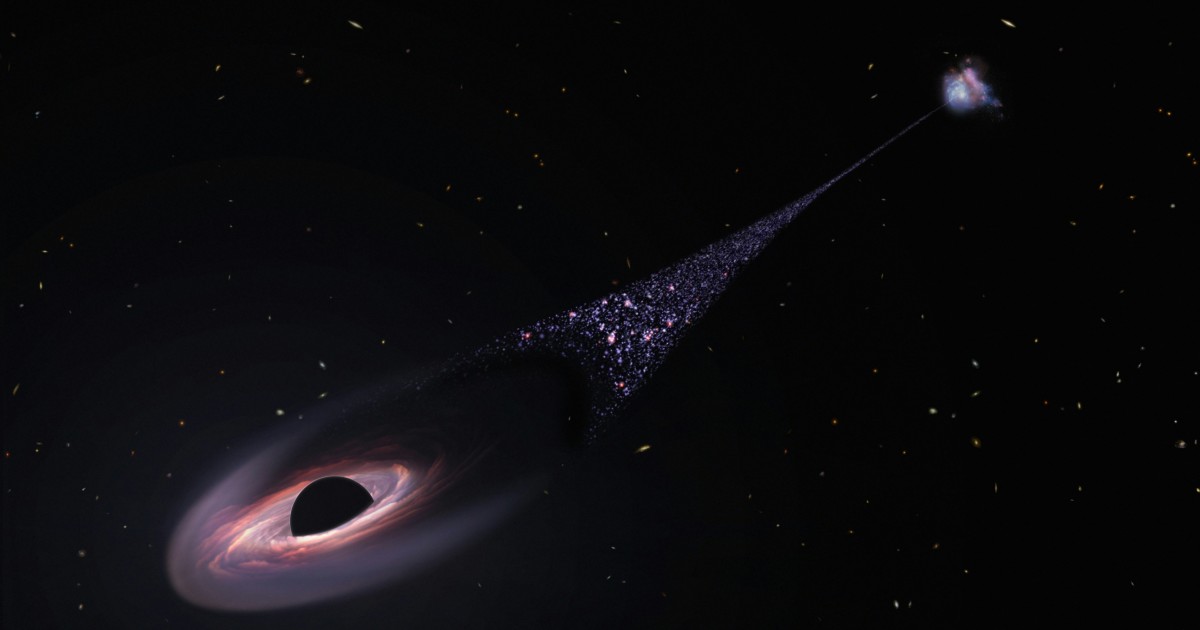ストラディバリウスの音色を求めて【第37号】
【140字まとめ】今週は「音の色」つまり音色(おんしょく)に関するストーリーです.ベルたちによる電話の発明から,モーグによる伝説のシンセサイザーの開発,そしてミュージシャン冨田勲とロケット工学の話をさせていただきます.最後に数学者フーリエと古代エジプトの関係も.
いちです,おはようございます.

シャーロック・ホームズ(左)とワトスン博士(右) (BBC)
お休みを頂いていた間に,新訳をまだ読んでいなかった「シャーロック・ホームズ」全集(60話)と,公式続編となる「絹の家」と「モリアーティ」を一気読みしまして,いま「ホームズ・ロス」に陥っています.パスティーシュ作品へ行くか,はたまたライバル作品へ手を出すか,悩ましいところです.20代の頃は粋がってホームズを原著で読んでみましたが,あれは日本で言えば夏目漱石以前の作品を読むようなもので,あまり英語の勉強にはなりませんでした.だいたい文字からして英語版の旧仮名遣いです.やはり英語の勉強には近代的な作品が良いでしょうね.個人的にはハリー・ポッターがおすすめです.
ところでシャーロック・ホームズを通しで読むと,作者の腕がどんどん上達していくことがわかって安心します.かのワトスン博士もデビュー作では語り下手なので,徐々にクオリティを上げていけばいいのだなと思えます.このニュースレターのクオリティも徐々に上がっていくことを願っているのですが,どうでしょうか…
音の色?
さて,今週は「音の色(いろ)」の話をしてみたいと思います.
ミュージシャンによっては,音に「色」が見えるそうです.音階ではなくて,例えばバイオリンの音なら「水色」というふうに,楽器ごとに色があるそうなんです.もちろん,音階の色が見えるミュージシャンもいらっしゃいますが,今回のお話は楽器ごとの色のお話です.

この記事は無料で続きを読めます
- グラハム・ベルと電話
- ロバート・モーグとシンセサイザー
- 冨田勲とロケット工学
- 数学者フーリエの考えたこと
- おすすめ書籍
- おすすめTEDxパフォーマンス
- Q&A
- 振り返り
- あとがき
すでに登録された方はこちら