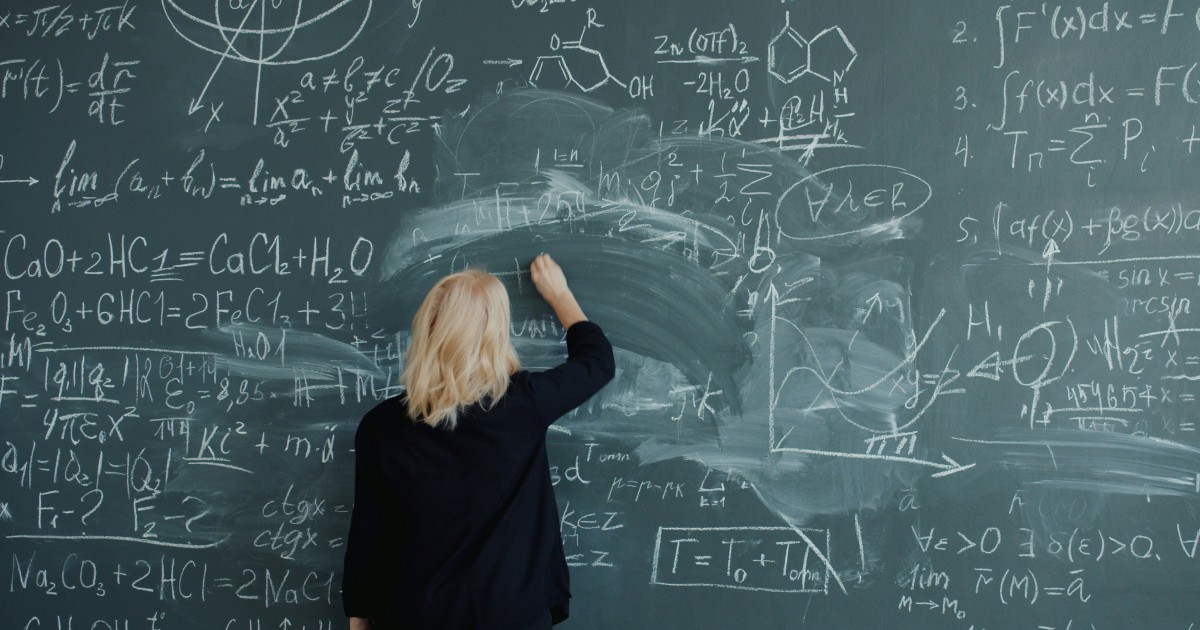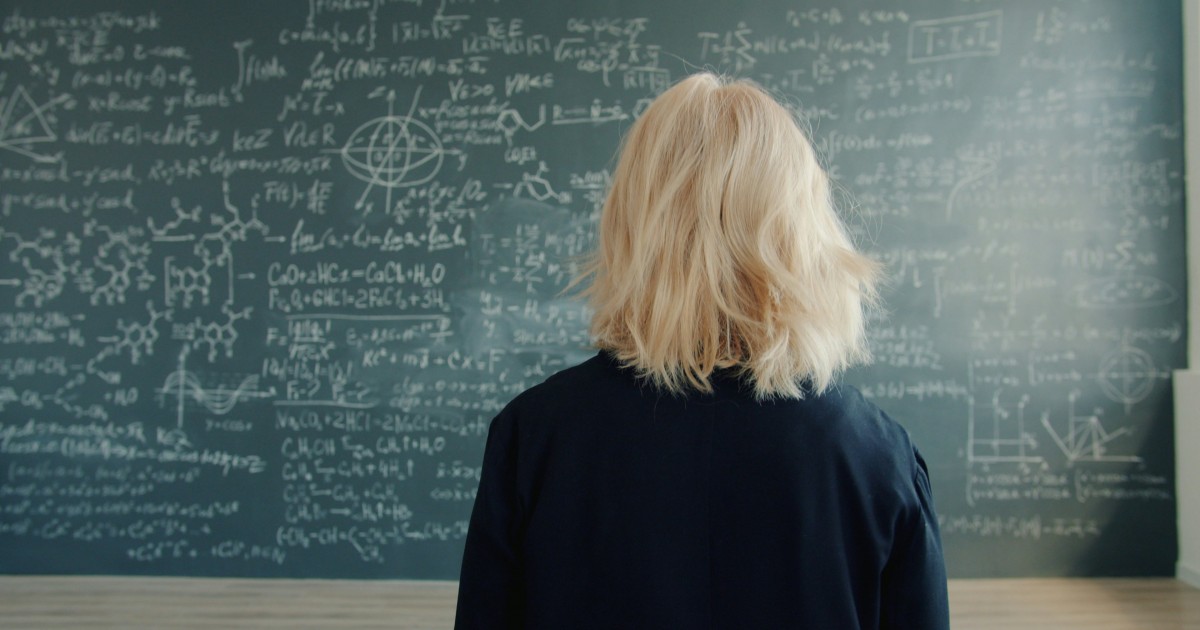緑色のひみつ【第96号】
【140字まとめ】タイの名高い仏教寺院ワット・プラケーオには緑色に輝く「エメラルド仏」があります.実際にはエメラルドではなく玉(ぎょく)すなわちヒスイでできた仏様ですが,どうして緑色なのでしょうか?東アジアで緑がもっとも高貴な色とされていた理由を無理矢理(?)推測してみました.
STEAM NEWS はメールで毎週届くニュースレターです.国内外のSTEAM分野(科学・技術・工学・アート・数学)に関するニュースを面白く解説するほか,今週の書籍,TEDトークもお届けします.芸術系や人文系の学生さんや教育関係者の方,古代エジプト好きな方にとくにおススメです.
いちです,おはようございます.
洪水のバンコクから帰国したところ,長崎の自宅で強烈な台風に遭遇しました.どうもそういう星の下に生まれたようです.

エメラルド仏 (By กสิณธร ราชโอรส - Own work, CC BY-SA 4.0)
ところで,バンコクには大変に名高い仏教寺院「ワット・プラ・ケオ」があります.ワット・プラ・ケオは,緑色に輝く「エメラルド仏(ぶつ)」が安置されているため「エメラルド寺院」の別名を持っています.「エメラルド」と呼ばれてはいますが,この仏様,実際にはヒスイ(翡翠)でできています.英語にしたときの知名度や高級感から,ヒスイ (Jade) よりもエメラルド (Emerald) の名を冠したのでしょうね.
中国や日本ではこのヒスイのことを「玉(ぎょく)」とも言います.

ネフライト (By Cp9asngf, CC BY-SA 4.0)
中国のヒスイは学術的にはネフライトという石のことなのですが,日本では,中国では産出しないジェダイトというネフライトによく似た石も産出します.そして,ややこしいことに日本ではネフライトとジェダイトをまとめてヒスイと呼びます.それどころか,中国でも日本から輸入されたジェダイトをヒスイと呼ぶのです.

ジェダイト (By Cp9asngf, CC BY-SA 4.0)
どっちやねーん,てなりますよね.
ジェダイトはネフライトよりも硬いため,区別するときはジェダイトを硬玉,ネフライトを軟玉と呼びます.この路線で行くと,より硬いエメラルドは「超硬玉」になるでしょうか.
さて,今週はこの緑色の輝石について,お話ししてみます.
【お知らせ】ツイッターで「STEAMコミュニティ」を運営しています.ときどき裏話をつぶやいています.ツイッターアカウントをお持ちの方は是非ご参加ください.
《目次》
-
糸魚川のヒスイ
-
緑は高貴な色なの?
-
なぜ「緑い」と言わないの?
-
今週の音楽
-
今週のTEDxトーク
-
Q&A
-
一伍一什のはなし

この記事は無料で続きを読めます
- 糸魚川のヒスイ
- 緑は高貴な色なの?
- なぜ「緑い」と言わないの?
- 今週の音楽
- 今週のTEDxトーク
- Q&A
- 一伍一什のはなし
すでに登録された方はこちら