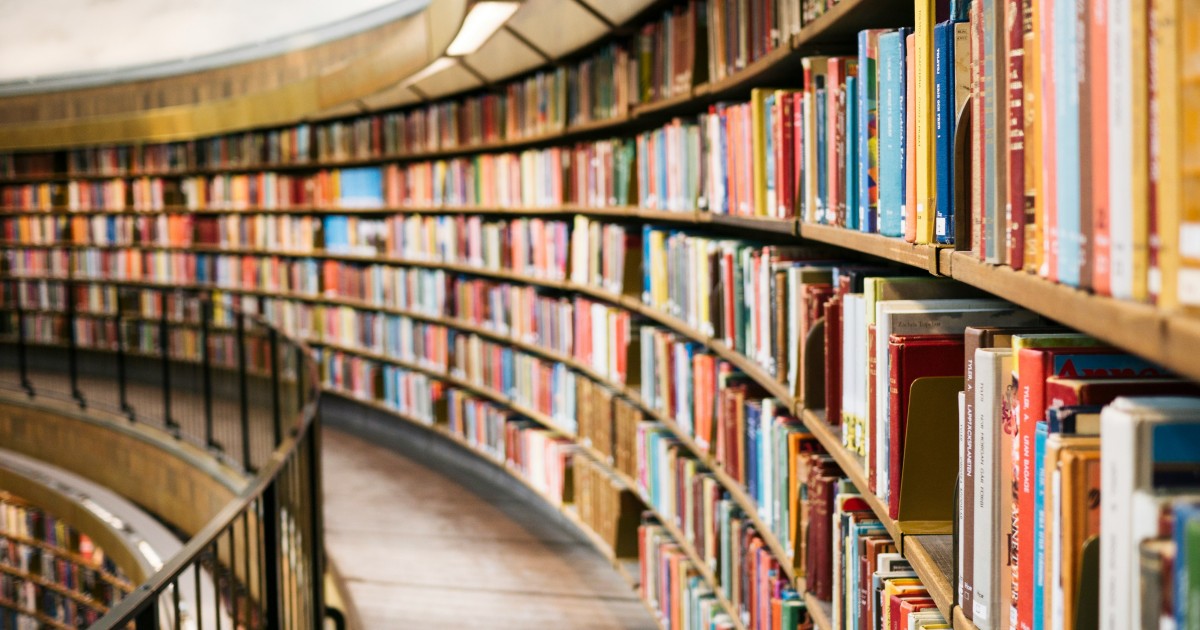【第17号】ゼロから文明を作り出せ!
この世界が消えたあとの「長崎ちゃんぽん」の作り方
いち
2021.04.09
読者限定
いちです,おはようございます.
新年度が始まりました.僕の勤める長崎大学にも日本中から新入生が集まっています.外国からの入学生がキャンパスに足を運ぶのはもう少し先になりそうですが,おいおい集まってくるでしょう.
昨年,オンライン受験相談に来た高校生から「なぜ長崎ちゃんぽんは美味いんですか?」と聞かれました.
「ちゃんぽん」美味しいですよね.この「なぜ長崎ちゃんぽんは美味いのか」というのは,とても深い質問なのです.今週は長崎ちゃんぽんに使われる「ちゃんぽん麺」の秘密を通して,日本に国があるという奇跡,そして,この世界が消えたあと文明を取り戻す方法を共有したいと思います.

この記事は無料で続きを読めます
続きは、9979文字あります。
- 特異な国「日本」
- 日本に無かったもの
- 日本式ラーメンと長崎ちゃんぽん
- この世界が消えたら?
- 石鹸を作る
- 世界は終わるの?
- おすすめ書籍
- おすすめTEDトーク
- Q&A
- あとがき
- 参考文献
すでに登録された方はこちら