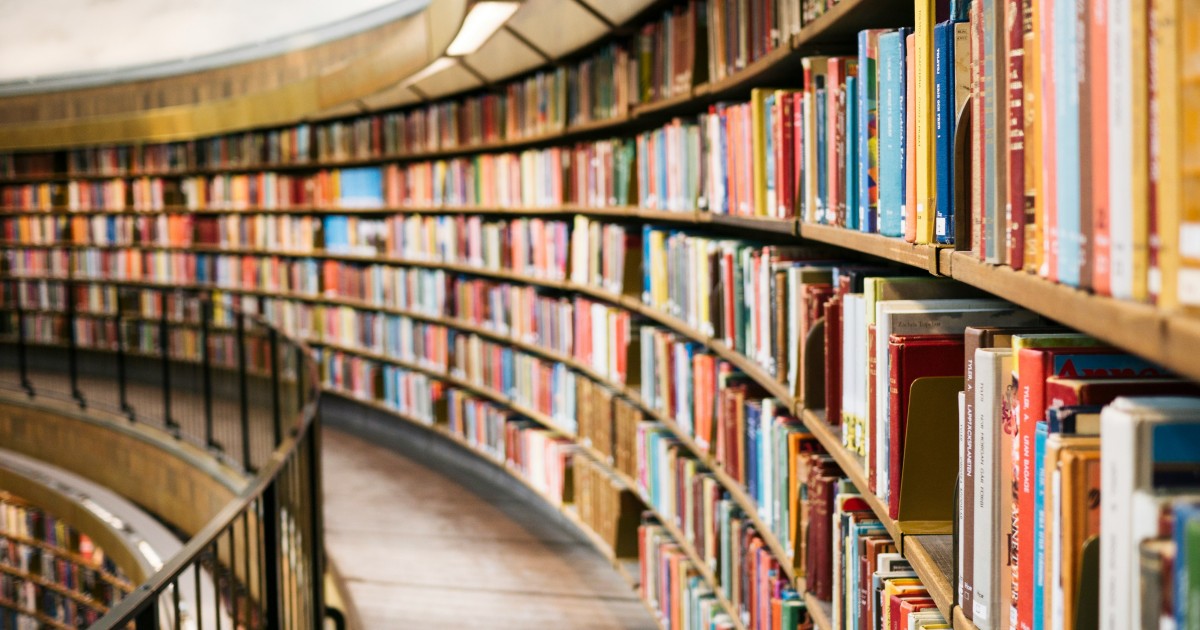古代エジプト人たちの見た七つの惑星たち【第85号】
【140字まとめ】古代エジプト人たちは天体の動きを注意深く観測しました.そして太陽と月をあわせた「七つの惑星」を地球から遠い順に並べることに成功していたようです.またアレクサンドリアの女性天文学者ヒュパティアは天体の動きを再現する装置まで発明していました.この観測は,やがて地動説へと繋がります.
STEAM NEWS はメールで毎週届くニュースレターです.国内外のSTEAM分野(科学・技術・工学・アート・数学)に関するニュースを面白く解説するほか,おすすめ書籍,TEDトークもお届けします.芸術系や人文系の学生さんや教育関係者の方,古代エジプト好きな方に特におすすめです.
いちです,おはようございます.
先月登壇させて頂いたTEDxKobeの動画がアップされました.魅力的なトークやパフォーマンスがぎっしりですから,是非楽しんで下さい.
さて,今週とても美しい写真が届きました.「惑星パレード」です.

京都大学 OASES project
写真には水星,金星,天王星,火星,木星,海王星,土星,月が並んでいます.海王星は肉眼で見るには暗すぎ,天王星もぎりぎり見えるか見えないかぐらいの明るさなのですが,この五つの惑星と月,そしてもうすぐ登ってくる日(太陽)は,コペルニクス,ケプラー,そしてガリレオ・ガリレイといった地動説を唱えた科学者たち以前の人類にとって,特別な存在でした.
2022年6月は,惑星が勢揃いする月だったのですね.
今週はそんな七つの「惑星」についてのお話をお届けします.
本ニュースレターは「STEAMボート」乗組員(STEAM NEWS有料購読者様)のご支援でお届けしております.乗組員の皆様に感謝申し上げます.
【お知らせ】ツイッターで「STEAMコミュニティ」を運営しています.時々裏話をつぶやいています.ツイッターアカウントをお持ちの方は是非ご参加ください.
《目次》
-
古代エジプトの天文学
-
地球から7惑星までの距離と曜日の関係
-
エジプトの天才天文学者「ヒュパティア」
-
おすすめ書籍:ゆるゆる神様図鑑 古代エジプト編
-
おすすめTEDトーク:光害問題を解決する簡単な5つの方法(日本語字幕)
-
Q&A
-
一伍一什のはなし

この記事は無料で続きを読めます
- 古代エジプトの天文学
- 地球から7惑星までの距離と曜日の関係
- エジプトの天才天文学者「ヒュパティア」
- おすすめ書籍
- おすすめTEDトーク
- Q&A
- 一伍一什のはなし
すでに登録された方はこちら