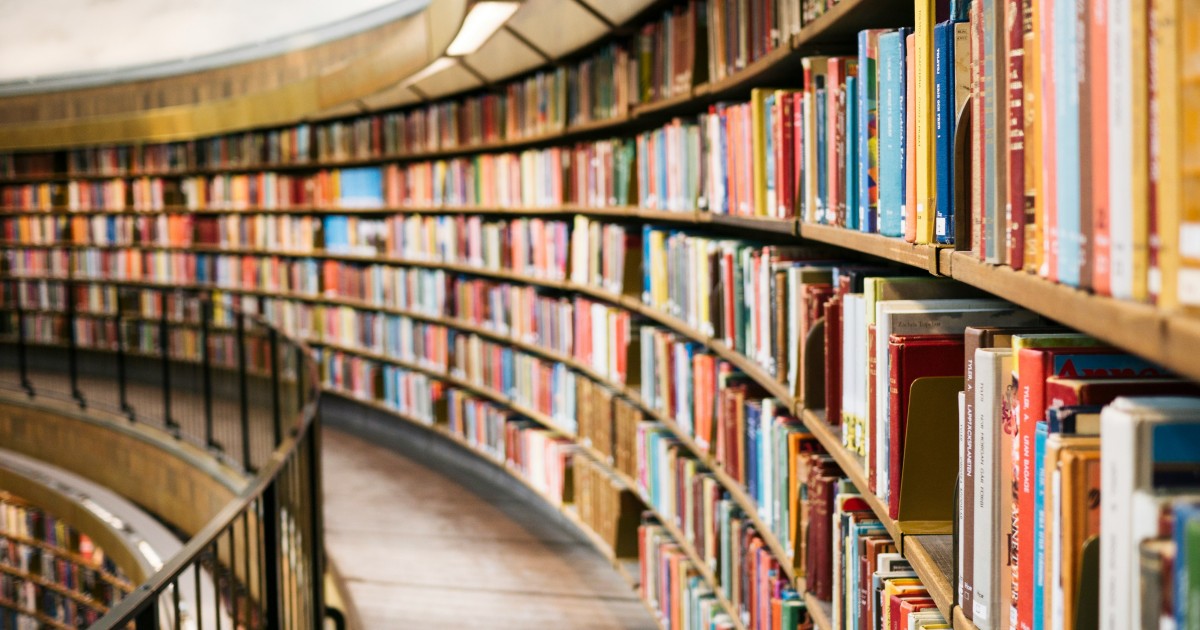オリンピック開会式のドローン・ディスプレイ【第35号】
スター・ウォーズの「レイア姫」からドローン・ディスプレイまでの道のり
いち
2021.07.30
読者限定
【140字まとめ】今週は東京オリンピック開会式で空中に地球を出現させた「ドローン・ディスプレイ」の話題です.アメリカ製なの?どうしてラジコンヘリじゃないの?どうやってディスプレイになってるの?GPSは使ってるの?空中ディスプレイて他にどんな種類があるの?などの疑問にお答えしてみます.
いちです,おはようございます.
兎にも角にも東京オリンピックが始まりましたね.開会式の演出をご覧になった方も多くいらっしゃることでしょう.普通,この手のショウは花火に全部「持っていかれる」ものなのですが,それでも特にドローンを使った特大の空中ディスプレイは圧巻でした.
このドローンによる表現には「さすが日本の技術」(違います)や「日本の技術はもっと進んでいる」(これも違います)などちょっとずれた感想も寄せられています.
今週はこの東京オリンピック開会式の演出に使われた技術について,公開されている資料から解説してみます.

この記事は無料で続きを読めます
続きは、6540文字あります。
- 東京オリンピック開会式のドローンはアメリカ製?
- 飛んで止まるということ
- 自分の位置を知るということ
- 空中ディスプレイあれこれ
- おすすめ書籍
- おすすめTEDトーク
- Q&A
- 振り返らない動画
- あとがき
すでに登録された方はこちら