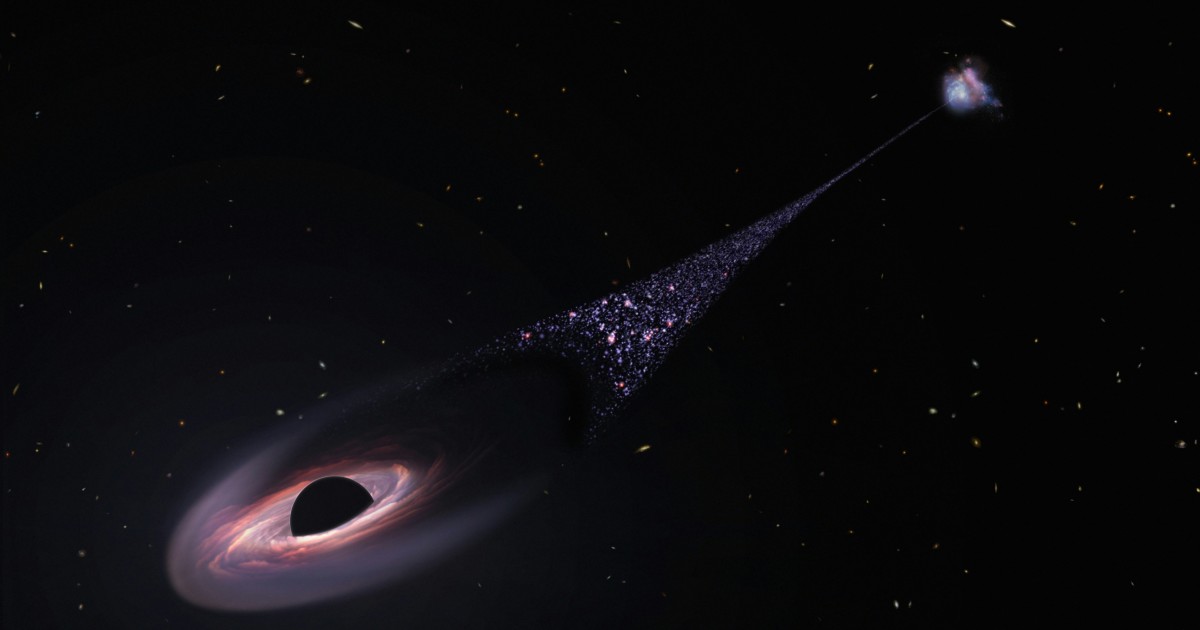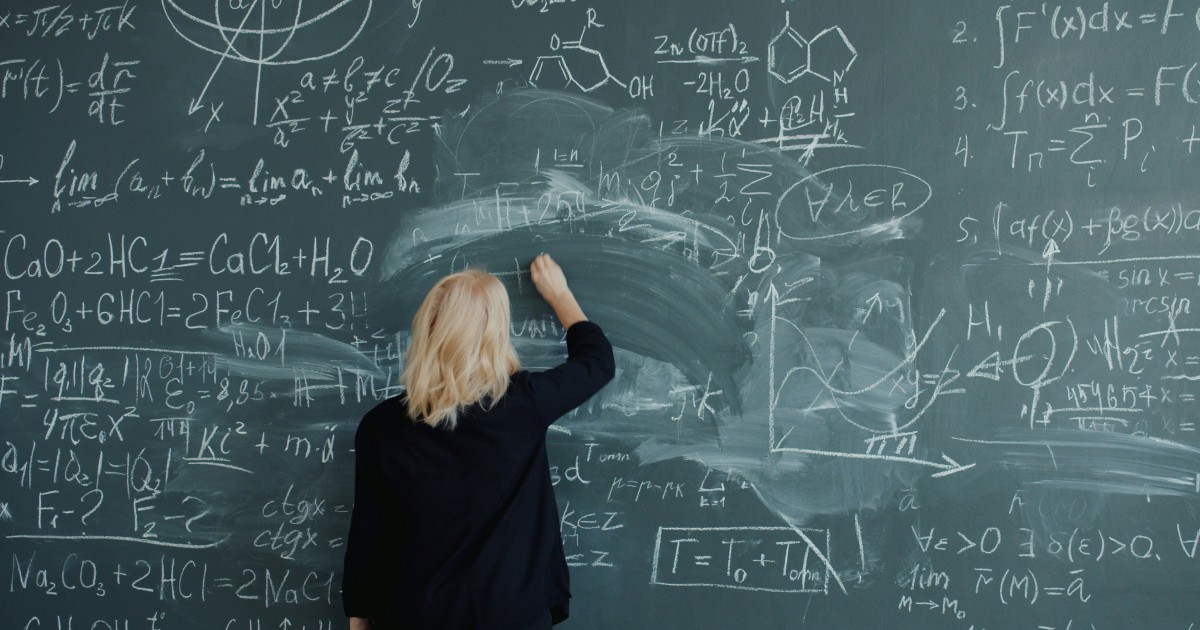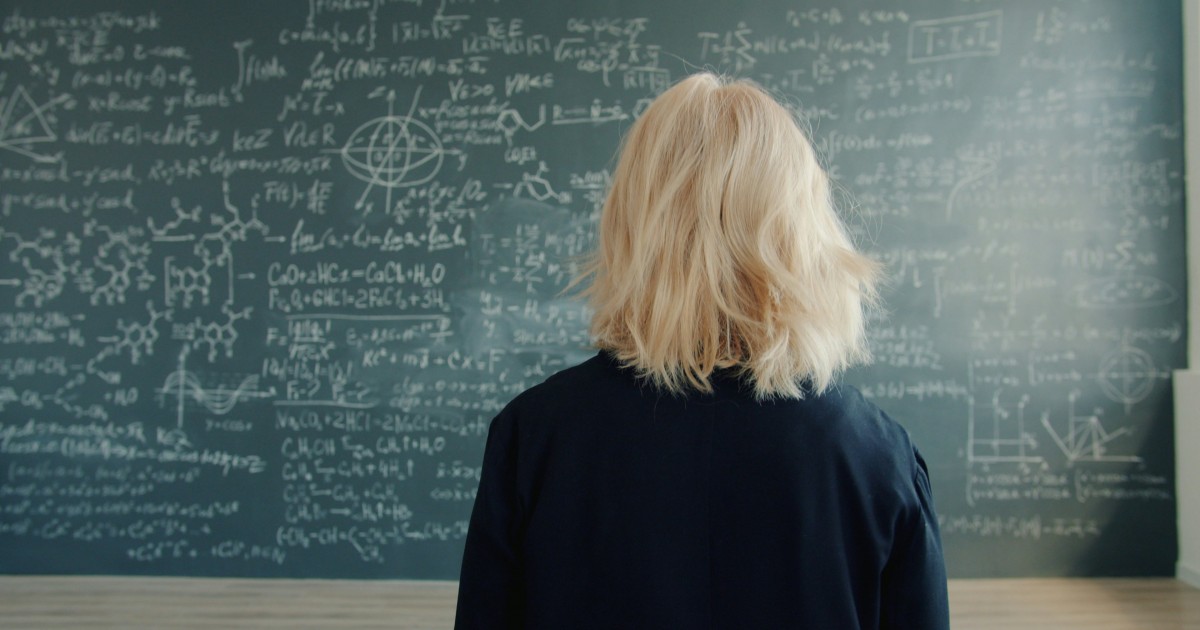「アート思考」て何だ?クリエイティビティ・コンパスが指し示す「禅」への道【第70号】
【140字まとめ】多くの人が誤解している「アート思考」について,今週はMITメディアラボのジョン・マエダ元副所長,伊藤穣一元所長の発言を元に解説します.アート思考は「アーティストの制作プロセスを真似る」ことですが,この「制作プロセス」はおそらく,全く理解されていないのです.
STEAM NEWS は毎週届くニュースレターです.国内外のSTEAM分野(科学・技術・工学・アート・数学)に関するニュースを面白く解説するほか,おすすめ書籍,TEDトークもお届けします.芸術系や人文系の学生さんや教育関係者の方,古代エジプト好きな方に特におすすめです.
いちです,おはようございます.
暖かくなってきましたね.
ロシアにいる僕の友人のひとりは,いまはロシアを出国してジョージアで仕事を続けているそうです.この点では少し安心はするものの,内心戦争に反対しているであろうロシア人たちの気持ちを考えると,改めて「政体」というものについて考えさせられます.クリストファー・ノーラン監督の映画「ダークナイト」の中で,僕のヒーロー「ユリウス・カエサル」のことを「彼はディクタトール(dictator)よ」と非難するシーンがありました.ディクタトールはラテン語で「非常時の執政官」の意味ですが,英語に直訳したディクテーター(dictator)には「暴君」の意味もあります.
イギリスの元首相ウィンストン・チャーチルは「民主主義は最悪の政治形態である.他に試みられたあらゆる形態を除けば」と言っています.なるほど,民主主義は決断が遅く,政策の効果は少なく,簡単に愚衆政治に陥ります.それでもなお,ロシアのような事実上の君主制に比べれば,よほど国民を幸福にし,世界平和に貢献する政体と言えるでしょう.
ニュースレターには本来「まくら」は不要で,いきなり本題に入るべきなのですが,ついつい思いの丈を書いてしまいました.どうかお許し下さい.
さて,今週は多くの人が誤解している「アート思考」について考えてみたいと思います.このニュースレターは毎週ファクトにもとづいた説明を心がけているのですが,今週は思いっきり僕の主観でお話しします.疑問点がありましたら,下のお知らせにある「STEAMコミュニティ」でも,このニュースレターの最後にある匿名質問箱でも,おたずね頂ければ幸いです.
【お知らせ】ツイッターで「STEAMコミュニティ」を開始しました.アカウントをお持ちの方は是非ご参加ください.匿名でもご参加いただけます.
《目次》
-
クリエイティビティ・コンパス
-
エプスタイン事件について
-
おすすめ書籍:ピクサー〜早すぎた天才たちの大逆転劇
-
おすすめTEDトーク:革新的なことをしたいなら「ナウイスト」になろう
-
Q&A
-
一伍一什のはなし

この記事は無料で続きを読めます
- クリエイティビティ・コンパス
- エプスタイン事件について
- おすすめ書籍:ピクサー〜早すぎた天才たちの大逆転劇
- おすすめTEDトーク:革新的なことをしたいなら「ナウイスト」になろう
- Q&A
- 一伍一什のはなし
すでに登録された方はこちら