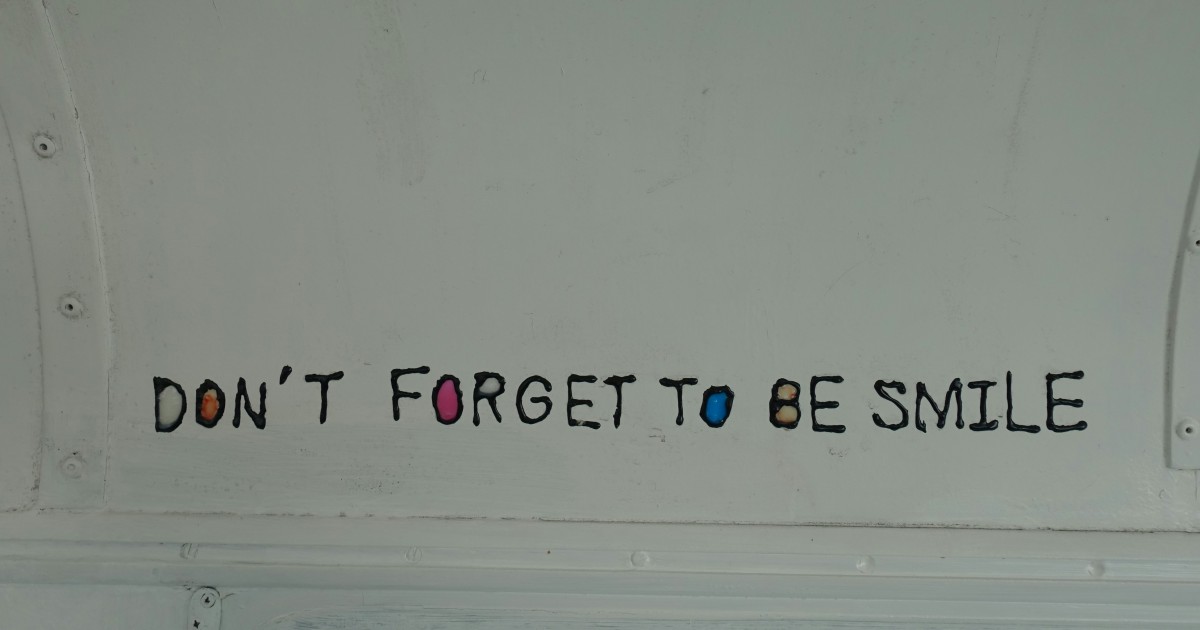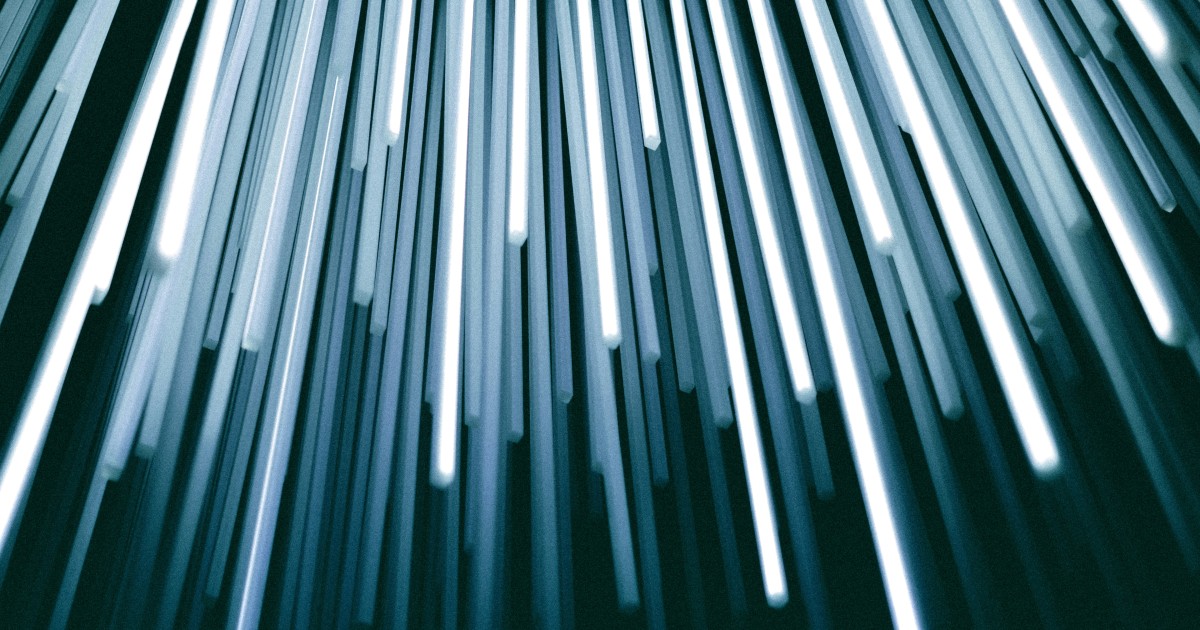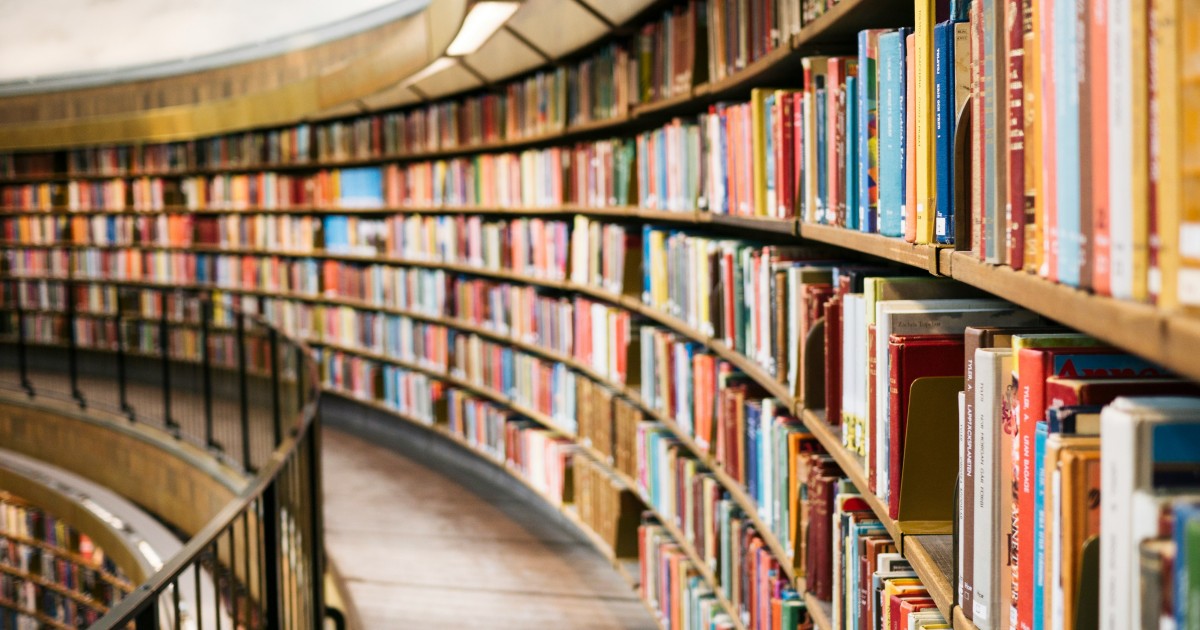【第21号】お酒
お酒にまつわる科学とアートのお話
いち
2021.05.07
読者限定
いちです,おはようございます.
最近,お酒にまつわる驚きのニュースがふたつ飛び込んできました.
ひとつめのニュースは「おいおい,現代に『禁酒法』かよ」というニュースでした.政府は2021年4月25日から5月11日の間,東京都,大阪府,兵庫県,京都府に対して「緊急事態宣言」を発出しました.東京都はさらに,緊急事態宣言の期間中は飲食店に対して酒類の提供を取りやめるよう要請しました.(この緊急事態宣言は5月末まで延長される模様で,対象地域も拡大されそうです.)
なお飲酒は禁止されていないので,自宅で飲む分には問題ないことになります.「禁酒法」の名で知られるアメリカ合衆国憲法修正第18条およびボルステッド法は酒類の製造,販売,輸送,輸出入などを禁じたのですが,飲酒そのものは禁止しませんでしたので,東京都の要請を禁酒法になぞらえるのも間違いとは言い切れません.

この記事は無料で続きを読めます
続きは、11826文字あります。
- お酒と錬金術
- お酒の始まり
- 穀物から造るお酒
- 蒸留酒
- ギムレットには早すぎる?
- 酒で人生が狂った科学者たち
- 木からエタノール
- 酒とアート
- おすすめ書籍
- おすすめTEDトーク
- Q&A
- 振り返り
- あとがき
- 参考文献
すでに登録された方はこちら