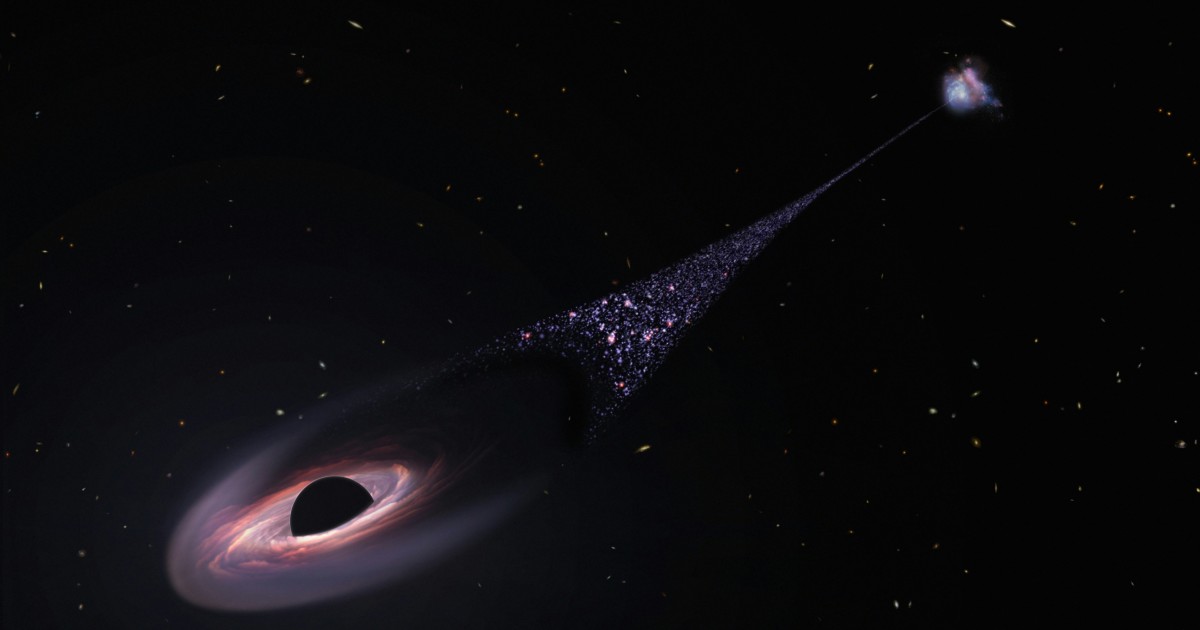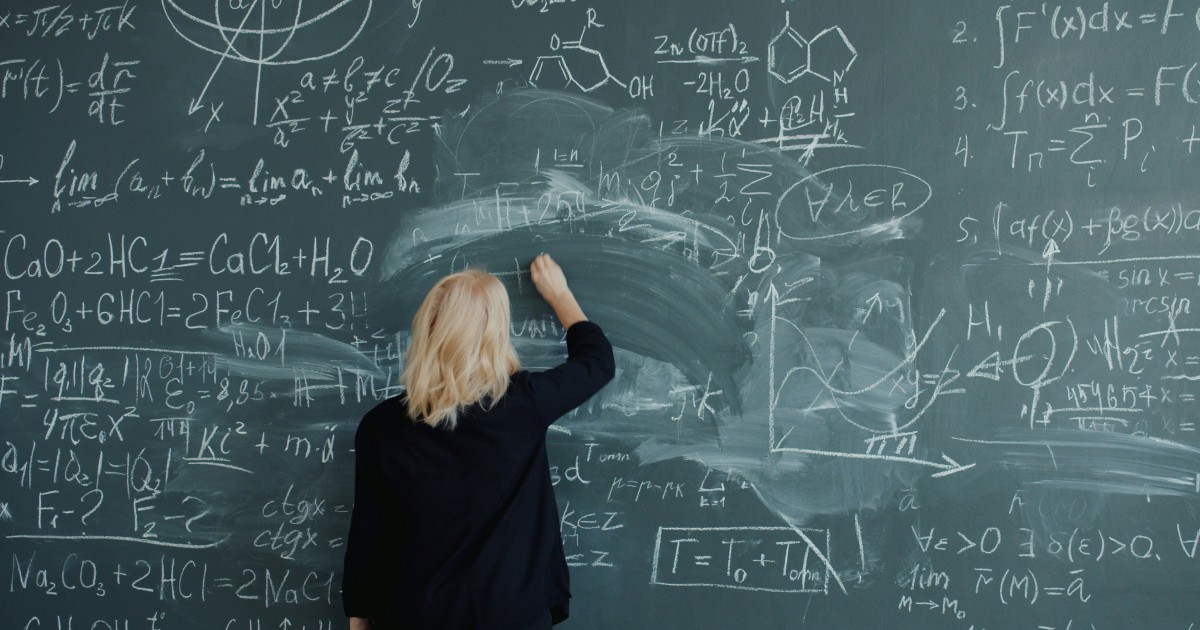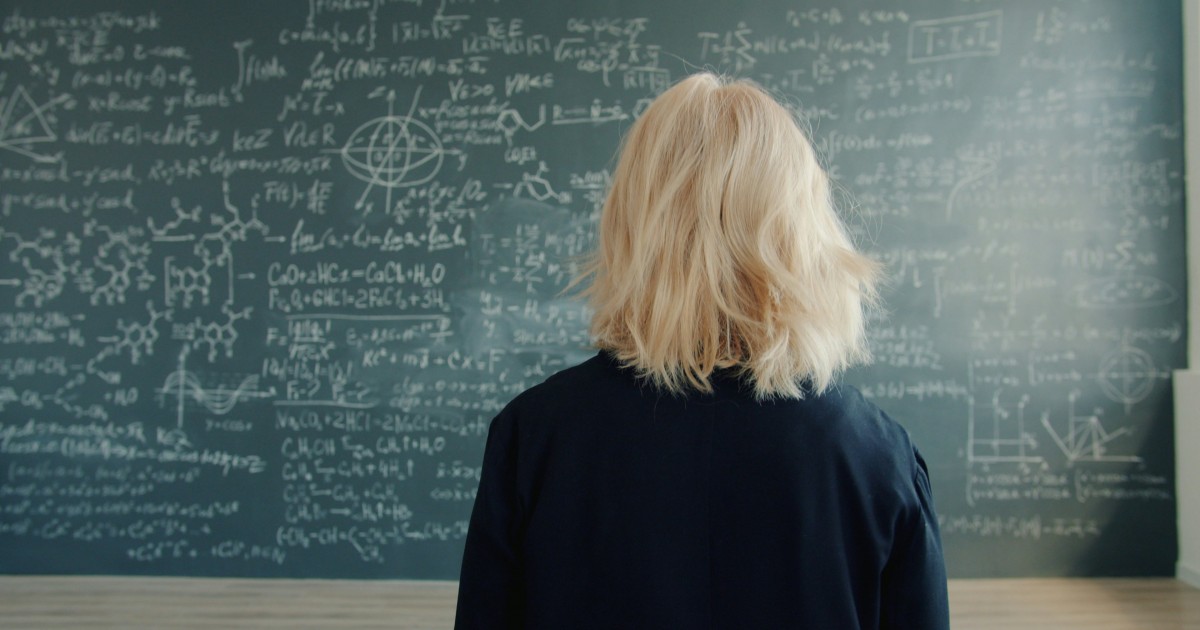仕事を片付けろ:Getting Things Done【第146号】
2️⃣ひとつめ:時間割を切ること
3️⃣ふたつめ:明日できることは今日しないこと
※メールでお送りした記事では一部「見出し」が抜けておりました.訂正版を掲載いたします.
いちです,おはようございます.
昨夜,阪神タイガースが優勝(アレ)しました.わーい.

虎テレ
この原稿は甲子園球場の阪神巨人戦を見ながら書いていました.ところどころおかしなところがあるかと思いますが,タイガースファンの特殊事情ということでお許しいただければ幸いです.まだ「クライマックスシリーズ」があるとは言え,18年ぶりのアレなもので……
さて,今週のテーマは「仕事を片付けろ」です.注意力「超」散漫な僕が,どうやって仕事を片付けているのか,いつもと趣向を変えて,簡単にご紹介させていただこうと思います.
1990年代の人気TV番組「料理の鉄人」をご記憶でしょうか? 料理人同士が決められた食材で対決する番組です.レギュラー料理人,つまり「鉄人」だった和食担当の道場六三郎さんは現在YouTuberとして活躍もされています.
僕は「最強の鉄人」とも呼ばれた道場六三郎さんから学んだことがひとつあるのです.彼は料理を始める前に,制限時間があるにもかかわらず,いつも「お品書き」を書き上げるのです.これは,あらゆる仕事の「コツ」かもしれません.
📬 STEAM NEWS は国内外のSTEAM分野(科学・技術・工学・アート・数学)に関するニュースを面白く解説するニュースレターです.
-
仕事のやり方ってどこで習うのだろう?
-
どんな方法も破綻はする
-
GTDで出来ないこと
-
今週の書籍
-
今週のTEDトーク
-
Q&A
-
一伍一什のはなし
この記事は無料で続きを読めます
- 仕事のやり方ってどこで習うのだろう?
- どんな方法も破綻はする
- 今週の書籍
- 今週のTEDトーク
- Q&A
- 一伍一什のはなし
すでに登録された方はこちら