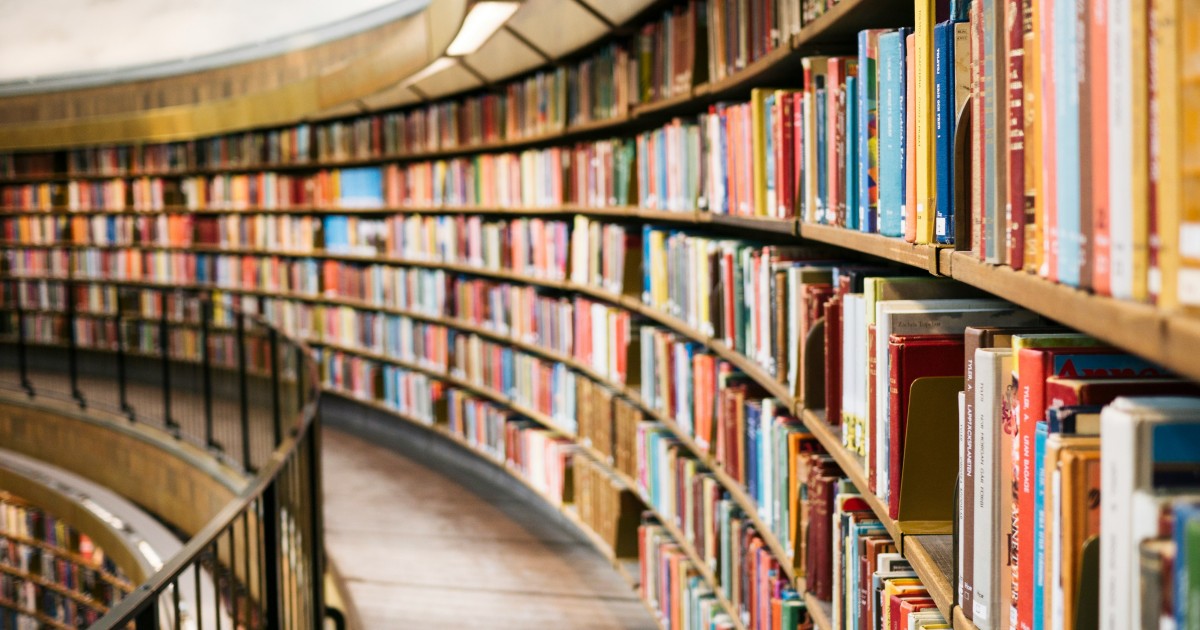第7の芸術・第4の科学【第137号】
2️⃣いま「第4科学」と呼ばれる「データ科学」が誕生しています
3️⃣僕たちは「次の芸術」「次の科学」を見られるかもしれません
いちです,おはようございます.
角川武蔵野ミュージアムで「体感型古代エジプト展 ツタンカーメンの青春」が始まりました.河江肖剰先生(ゆきさん)の紹介動画もありますので,ぜひご覧になってくださいね.

さて,今週は「第7の芸術」と「第4の科学」についてお話をします.芸術や科学に番号がついているのってなんかヘンだと思いますよね? でも芸術家や科学者の間ではなんとなく合意が取れているナンバリングなんです.
先に答えを言ってしまうと,第7芸術とは「映画」のこと,第4科学とは「データ科学」のことなんです.
ふむ.もう少し掘り下げていきましょう.
【お知らせ】8月13日に長崎県美術館でTEDxDejima EDイベントを開催します.招待制ですので,招待コードをご希望の方は7月21日までに本メールアドレスへご返信ください.数に限りがあります.
📬 STEAM NEWS は国内外のSTEAM分野(科学・技術・工学・アート・数学)に関するニュースを面白く解説するニュースレターです.
《目次》
-
第7の芸術:映画
-
第4の科学:データ科学
-
第7芸術の先・第4芸術の先
-
今週の書籍
-
今週のTEDトーク
-
Q&A
-
一伍一什のはなし
この記事は無料で続きを読めます
- 第7の芸術:映画
- 第4の科学:データ科学
- 第7芸術の先・第4芸術の先
- 今週の書籍
- 今週のTEDトーク
- Q&A
- 一伍一什のはなし
すでに登録された方はこちら