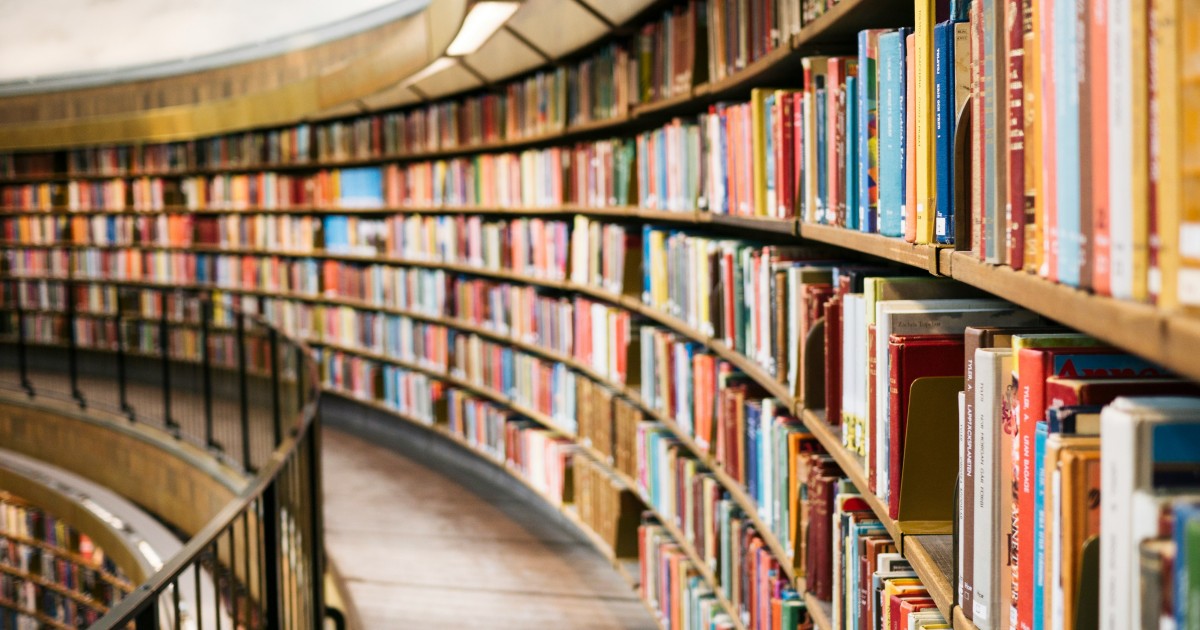花火の科学【第36号】
【140字まとめ】夏といえば(今年は見られないけれど)花火.今週は花火のルーツである狼煙,打上花火の秘密,そして花火に使われる炎色反応についてお話します.最後に,内側に向かって爆発する花火,つまりプルトニウム型原爆についてもお話します.
いちです,おはようございます.
夏といえば花火ですが,今年は,というか今年も,花火大会の中止が相次いでいます.線香花火ぐらいは楽しみたいところですが,屋内だとそれも難しいです.ここはひとつ「いちばん大事なところは想像で補う」という日本の様式美を思い出して,花火の音だけを楽しんではいかがでしょうか.Soundcloudに花火の音がアップされていたので,僕はこれを聞いています.
さて,今週はそんな花火にまつわるお話をお届けしようと思います.
花火のはじまり
花火のルーツは中国の「狼煙(のろし)」にあるとされています.紀元前214年に,秦の始皇帝によって建設が始まった「万里の長城」にも狼煙台があり,唐の時代(618年-907年)になると狼煙の文字記録もあります.この当時はもっぱら遠隔通信用に用いられたのでしょう.僕の中国人師匠は万里の長城の狼煙を「世界初の光通信」と呼んでいました.日本でも武田信玄が狼煙を活用したことで有名ですね.
一昨年,学生を世界遺産でもある長崎の野崎島に引率したときのことです.野崎島は事実上の無人島になっており,緊急時は近隣の小値賀島へ船を呼ばないといけません.もちろん電気のない島ですから,学生には「昼用」「夜用」の2種類の狼煙の上げ方を教えておきました.狼煙は白い煙のイメージが強いですが,昼間は白い煙て見えづらいんですよね.なので昼間はゴム製品を少量混ぜて燃やした黒い狼煙が推奨です.

無人島に取り残されたときは「スターファイヤー」というネイティブ・アメリカンの焚き火もおすすめ.
唐代あるいはそれより少し早くに火薬が発明されると(*),すぐに「爆竹」が開発されたようです.焚き火に竹をくべるとばちっ,ばちっと爆発しますよね.以前ベルギーから来た友人と無人島で焚き火をしたところ「これが日本のバンブーか!」と言って喜んでいましたが,この竹の弾け方と似ているので爆竹と呼んだのだそうです.長崎ではお盆の「精霊流し」のときに街中で爆竹を鳴らします.この爆竹がおそらく最古の花火だろうと言われています.
*後漢の時代に発明されたとする説もあります.