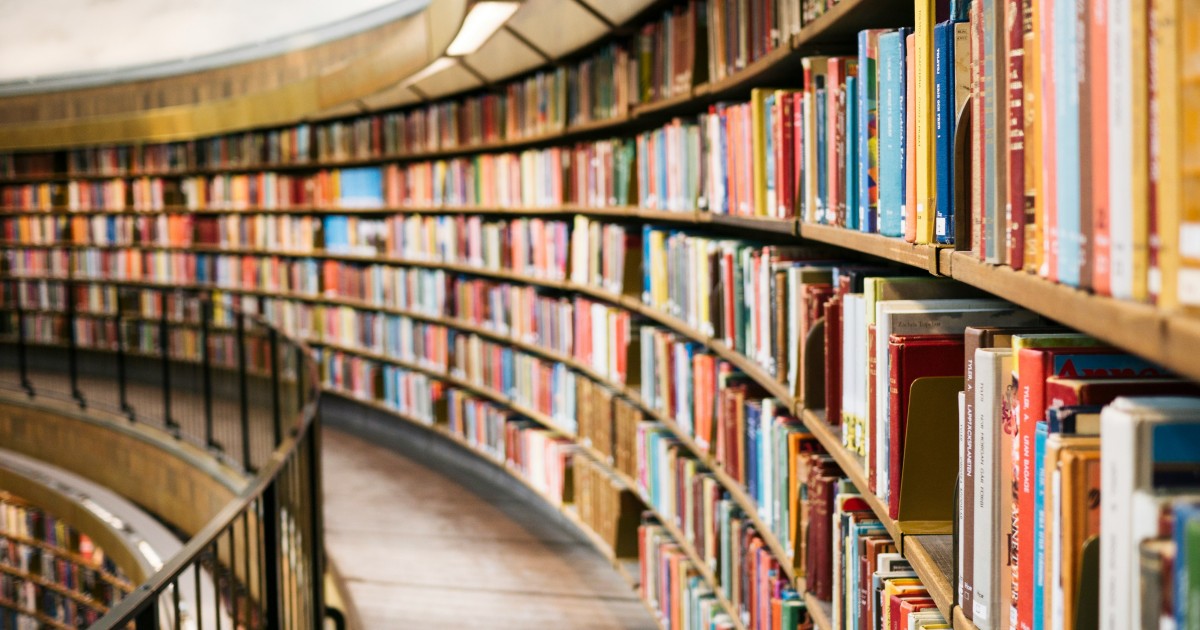【第7号】音楽がインスパイアした科学
いちです,おはようございます.
先月の話になりますが,地球から約40光年離れた星「TRAPPIST-1」の様子がより詳しくわかってきたようです.この星には7個の地球型惑星が発見されており,うち3個は地球と同じく「ハビタブルゾーン(生存可能圏)」にあると考えられています.もし人類が地球を脱出するとしたら,行き先候補になっている惑星系です.先月のニュースはこの7個の惑星の密度がほぼ等しいという発見でした.今週ご紹介する「TEDトーク」にもこの「TRAPPIST-1」が出てきますので,どうか最後までお付き合いください.
さて,今週は音楽が数学や科学に与えた影響をお話したいと思います.数学や科学が音楽に影響を与えたという話ではありません.その逆の話なのです.
テクノロジーが音楽を永遠に変えてしまった話は歴史にあふれています.エジソンの「蓄音機」は音の録音,再生を可能にする装置でしたが,この装置は「録音を前提に」演奏するという従来無かった演奏スタイルを生み出しました.エジソンが実用化した電気によって,エレクトリック・ギターのような電気楽器が次々と生まれていったこともご存知のとおりですし,同じく彼が発明した映画技術はミュージックビデオという新しい音楽メディアの基盤になりました.
科学にインスパイアされた音楽も世界にたくさんあります.冨田勲のアルバム「ドーン・コーラス」は太陽から吹き出す粒子「太陽風」が地球の磁気と作用するときに生じるノイズや,恒星からのパルス信号を音源にしています.(YouTubeで “Isao Tomita Dawn Chorus” で検索すると聞けます.)
これらの逆で「音楽が科学をインスパイアした」いくつかの事例を,今週はご紹介したいと思います.結果として,それらのうちふたつは間違っていて,ひとつは科学に革命を起こしました.
ここでお話するのは,音楽の基本要素である「音階」です.現在では数学や科学が音階を決めていますが,かつてその逆だったことがあるのです.

この記事は無料で続きを読めます
- 音階
- 2:1のあいだ
- 虹
- 元素
- 光
- 数学が決めた音律
- 科学にインスパイアされた音楽
- おすすめTEDトーク
- おすすめ(するかどうか迷っている)書籍
- Q&A
- ポッドキャストのお知らせ(+α)
- 【新年号】のフォローアップ
- あとがき
- 参考文献
すでに登録された方はこちら